「角を矯めて牛を殺す(つのをためてうしをころす)」ということわざがあります。
なんだか物騒な表現ですが、これは私たちが陥りがちな失敗を鋭く指摘しています。
一体どのような意味が込められているのでしょうか? このことわざの意味や由来、使い方について解説します。
「角を矯めて牛を殺す」の意味
このことわざは、「小さな欠点や些細な部分を無理に直そうとして、かえって全体をダメにしてしまうこと」のたとえです。
牛の角の形が少し曲がっているのを直そうとして、無理な力を加えた結果、牛そのものを死なせてしまった、という状況を思い浮かべてみてください。
些細な部分にこだわりすぎたために、もっと大切な本体や本質を台無しにしてしまうことを戒める言葉です。
つまり、「本末転倒」な行いや、手段が目的化してしまい、結果的に大きな損失を招くような状況を指して使われます。
「角を矯めて牛を殺す」の語源 – 古代中国の故事より
このことわざは、古代中国の故事に由来すると言われています。
その元となったのは、「牛の角の形がわずかに曲がっているのを、無理にまっすぐに直そう(=矯めよう)としたところ、力が強すぎて牛そのものを殺してしまった」という話です
(『説苑』などに見られる説)。
ここから転じて、小さな欠点を直そうとして、かえって物事全体や本質を損なってしまうことのたとえとして使われるようになりました。
「角を矯めて牛を殺す」が使われる場面と例文
このことわざは、些細なことにこだわりすぎて、本来の目的や全体の利益を損なうような状況を批判したり、戒めたりする際に使われます。
- 規則や形式への固執:規則を厳格に適用しすぎて、かえって非効率になったり、人間関係が悪化したりする。
- 過度な修正や編集:文章やデザインなどの一部を修正することにこだわり、全体のバランスや本来の良さを失ってしまう。
- 人材育成での失敗:部下や子供の小さな欠点を厳しく指摘しすぎて、やる気や自信を失わせてしまう。
- 政策や計画の実行:部分的な問題点にばかり対処して、全体の目標達成が妨げられる。
例文
- 「規則に厳格なのは良いが、角を矯めて牛を殺すようなことになっては本末転倒だ。」
- 「彼の文章は多少荒削りな部分もあるが、そこを直しすぎると角を矯めて牛を殺すことになりかねない。」
- 「新システムの導入は、細部にこだわりすぎて角を矯めて牛を殺す結果となった。」
「角を矯めて牛を殺す」の類義語
些細なことにとらわれて全体を見失う、本末転倒な状況を表す言葉です。
- 本末転倒:物事の根本と枝葉を取り違えること。最も意味が近い言葉の一つ。
- 木を見て森を見ず:部分ばかりに気を取られ、全体像を把握できないこと。
- 葉を欠いて根を枯らす:些細なこと(葉)のために、根本(根)をダメにしてしまうこと。
- 矯角殺牛(きょうかくさつぎゅう):このことわざをそのまま四字熟語にしたもの。
「角を矯めて牛を殺す」の対義語
直接的な対義語となることわざは少ないですが、このことわざが戒める状況とは逆の、適切な判断やバランス感覚を示す考え方があります。
- 大局観を持つ:物事の全体像や本質を見極めること。
- バランスを考える:部分と全体、手段と目的の調和を意識すること。
- (参考)長所を伸ばす:欠点を矯正することに固執せず、良い点に目を向けて育てるという考え方。
「角を矯めて牛を殺す」の英語での類似表現
英語にも、小さな問題に対処しようとして、より大きな問題を引き起こしてしまう状況を表すことわざや慣用句があります。
- Throw the baby out with the bathwater.
意味:風呂の水と一緒に赤ん坊まで捨ててしまう。不要なものを排除しようとして、大切なものまで失ってしまうたとえ。 - Burn down the house to roast the pig.
意味:豚の丸焼きを作るために家を燃やしてしまう。小さな利益のために、計り知れない損失を招くたとえ。 - The cure is worse than the disease.
意味:治療法が病気そのものより悪い。問題解決策が、元の問題よりも大きな害をもたらすたとえ。 - Penny wise and pound foolish.
意味:1ペニー(小銭)には賢いが、1ポンド(大金)には愚かである。小さなことには倹約するが、肝心なところで大損をするたとえ。
まとめ – 本末転倒を戒める教え
「角を矯めて牛を殺す」は、小さな欠点や枝葉末節にとらわれすぎると、かえって物事の本質や全体像を見失い、取り返しのつかない失敗を招くという、大切な教訓を私たちに伝えています。
何かを改善しようとする時、その目的は何か、本当に大切なものは何かを常に意識し、大局的な視点を持つことの重要性を教えてくれることわざと言えるでしょう。

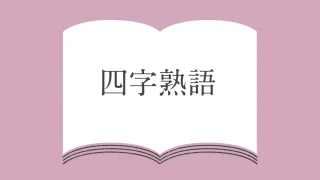

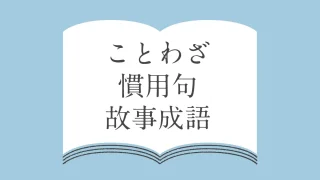
コメント