動物(哺乳類)に関係する有名なことわざ・慣用句の一覧
古くから人々と共に生きてきた動物たち。その姿や習性は、多くのことわざや慣用句となり、私たちの言葉を豊かに彩ってきました。
ここでは、そんな動物たちにまつわる言葉を、読み方と意味を添えて一覧にまとめました。日々の暮らしや文章表現のヒントになれば幸いです。
猫のことわざ・慣用句
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 猫に小判 (ねこにこばん) | 価値の分からない人に貴重なものを与えても、何の役にも立たないことのたとえ。 |
| 猫の手も借りたい (ねこのてもかりたい) | 非常に忙しく、どんな助けでもほしい状況のたとえ。 |
| 猫も杓子も (ねこもしゃくしも) | 誰も彼も、みんな揃って同じようなことをする様子。 |
| 窮鼠猫を噛む (きゅうそねこをかむ) | 追い詰められた弱い者も、必死になれば強い者に反撃することがあるというたとえ。 |
| 猫の目のように変わる (ねこのめのようにかわる) | 猫の瞳孔が光の加減で大きさを変えるように、状況や人の考えなどが目まぐるしく変わりやすいことのたとえ。 |
| 鰹節を猫に預ける (かつおぶしをねこにあずける) | 危険な状況を自ら作り出すこと。油断できない相手に大切なものを任せてしまうことのたとえ。「猫に魚の番」と似た意味。 |
| 猫に魚の番 (ねこにさかなのばん) | 猫に好物の魚の見張りをさせるように、油断できない状況や、危険な人に物事を任せることのたとえ。 |
| 猫の額 (ねこのひたい) | 猫の額のように、土地や場所が非常に狭いことのたとえ。 |
| 猫を追うより魚をのけよ (ねこをおうよりさかなをのけよ) | 問題が起きたとき、その場しのぎの対策をするのではなく、問題の根本原因を取り除くことが大切であるというたとえ。 |
| 猫を被る (ねこをかぶる) | 本性や悪意を隠して、おとなしそうに、あるいは知らぬふりをして見せかけること。 |
| 猫可愛がり (ねこかわいがり) | 理由もなく、むやみに相手を甘やかすこと。特に対象が子どもや孫などの場合によく使われます。 |
犬のことわざ・慣用句
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 犬も歩けば棒に当たる (いぬもあるけばぼうにあたる) | 何か行動を起こせば、思いがけない幸運(または災難)に出会うことがあるというたとえ。 |
| 飼い犬に手を噛まれる (かいいぬにてをかまれる) | 日頃から面倒を見たり、信頼していたりした人から裏切られたり、害を受けたりすることのたとえ。 |
| 犬猿の仲 (けんえんのなか) | 犬と猿のように、非常に仲が悪い関係のたとえ。 |
| 犬に論語 (いぬにろんご) | 道理の分からない人に何を教えても無駄であることのたとえ。「馬の耳に念仏」や「豚に真珠」と似た意味。 |
| 犬骨折って鷹の餌食 (いぬほねおって たかのえじき) | 苦労して得たものを他人に奪われてしまうことのたとえ。 |
| 犬兎の争い (けんとのあらそい) | 当事者同士が無益な争いをし、第三者に利益をさらわれることのたとえ。「漁夫の利」と似た状況を表す。 |
猿のことわざ・慣用句
豚、馬、牛、鹿のことわざ・慣用句
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 豚に真珠 (ぶたにしんじゅ) | 価値の分からない人に貴重なものを与えても無意味であることのたとえ。「猫に小判」とほぼ同じ意味。 |
| 馬の耳に念仏 (うまのみみにねんぶつ) | いくら意見や忠告をしても聞き入れようとしないことのたとえ。 |
| 馬脚を露わす (ばきゃくをあらわす) | 隠していた本性や悪事がばれること。「化けの皮がはがれる」と同じ意味。 |
| 生き馬の目を抜く (いきうまのめをぬく) | 油断も隙もない抜け目のない様子や、そのような人が多い世の中を指すこともある。 |
| 馬には乗ってみよ人には添うてみよ (うまにはのってみよひとにはそうてみよ) | 何事も自分で直接経験してみなければ、その本質は理解できないというたとえ。 |
| 九牛の一毛 (きゅうぎゅうのいちもう) | 非常に多くのものの中の、きわめてわずかな部分のたとえ。取るに足らないこと。 |
| 鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん (にわとりをさくに いずくんぞ ぎゅうとうをもちいん) | 小さなことを処理するのに、大げさな手段を用いる必要はないというたとえ。 |
| 鹿を追う者は山を見ず (しかをおうものは やまをみず) | 目先の利益や一つのことに心を奪われていると、他の大切なことや全体の状況を見失ってしまうというたとえ。 |
狐、狸のことわざ・慣用句
うさぎのことわざ・慣用句
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 二兎を追う者は一兎をも得ず (にとをおうものはいっとをもえず) | 同時に二つの目標を達成しようとすると、どちらも中途半端に終わってしまうというたとえ。 |
| 兎の上り坂 (うさぎののぼりざか) | 自分の得意な分野や状況で、力を存分に発揮できることのたとえ。 |
| 兎の耳 (うさぎのみみ) | 地獄耳であること、噂話などに非常に敏感なことのたとえ。また、単に情報の早さを指す場合もある。 |
| 犬兎の争い (けんとのあらそい) | 当事者同士が無益な争いをし、第三者に利益をさらわれることのたとえ。「漁夫の利」と似た状況を表す。 |
虎のことわざ・慣用句
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 騎虎の勢い (きこのいきおい) | 物事を始めた勢いで、途中でやめることができない状況のたとえ。 |
| 虎の尾を踏む (とらのおをふむ) | 非常に危険なことをするたとえ。 |
| 虎は死して皮を留め人は死して名を残す (とらはししてかわをとどめひとはししてなをのこす) | 人は死んだ後も、生前の行いや功績によって名声が残る。だから、名を惜しんで立派な行いをすべきだという教え。 |
| 虎穴に入らずんば虎子を得ず (こけつにいらずんばこじをえず) | 危険を冒さなければ、大きな成果や利益を得ることはできないというたとえ。 |
| 虎口を脱する (ここうをだっする) | 非常に危険な場所や状況から、かろうじて逃れること。 |
| 虎の威を借る狐 (とらのいをかるきつね) | (※「狐、狸のことわざ・慣用句」の項を参照) |
| 張り子の虎 (はりこのとら) | 見かけは強そうだが、実際には弱い者、首を縦に振るばかりで主体性のない者のたとえ。 |
獅子のことわざ・慣用句
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 獅子身中の虫 (しししんちゅうのむし) | 組織内部にいながら害をなす者や、恩を仇で返す者のたとえ。 |
| 獅子に鰭 (ししにひれ) | 強いものにさらに強さが加わることのたとえ。「鬼に金棒」と似た意味。 |
| 獅子は我が子を千尋の谷に落とす (ししはわがこをせんじんのたににおとす) | 本当に深い愛情があるからこそ、我が子に試練を与えて成長を促すことのたとえ。 |
その他の動物のことわざ
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 袋の鼠 (ふくろのねずみ) | 袋の中に追い詰められた鼠のように、逃げ道が全くなく、捕まるしかない状況のたとえ。 |
| 亀の甲より年の功 (かめのこうよりとしのこう) | 硬い亀の甲羅よりも、年長者の長年の経験の方が貴重であり、尊重すべきであるというたとえ。 |
| 群盲象を撫でる (ぐんもう ぞうをなでる) | 物事や人物の一部しか理解していないのに、全てを理解したかのように思い込んでしまうことのたとえ。「群盲象を評す」とも言う。 |
| 同じ穴の狢 (おなじあなのむじな) | 一見すると違うように見えても、実は同類であること。特に、悪事や良くないことを企む仲間同士を指すことが多い。 |
| 一匹狼 (いっぴきおおかみ) | 組織や集団に属さず、自分の力だけを頼りに独立して行動する人のたとえ。 |
| 羊の皮を被った狼 (ひつじのかわをかぶったおおかみ) | 外見は穏やかだが、本性は悪事を考えている人物をたとえ。 |

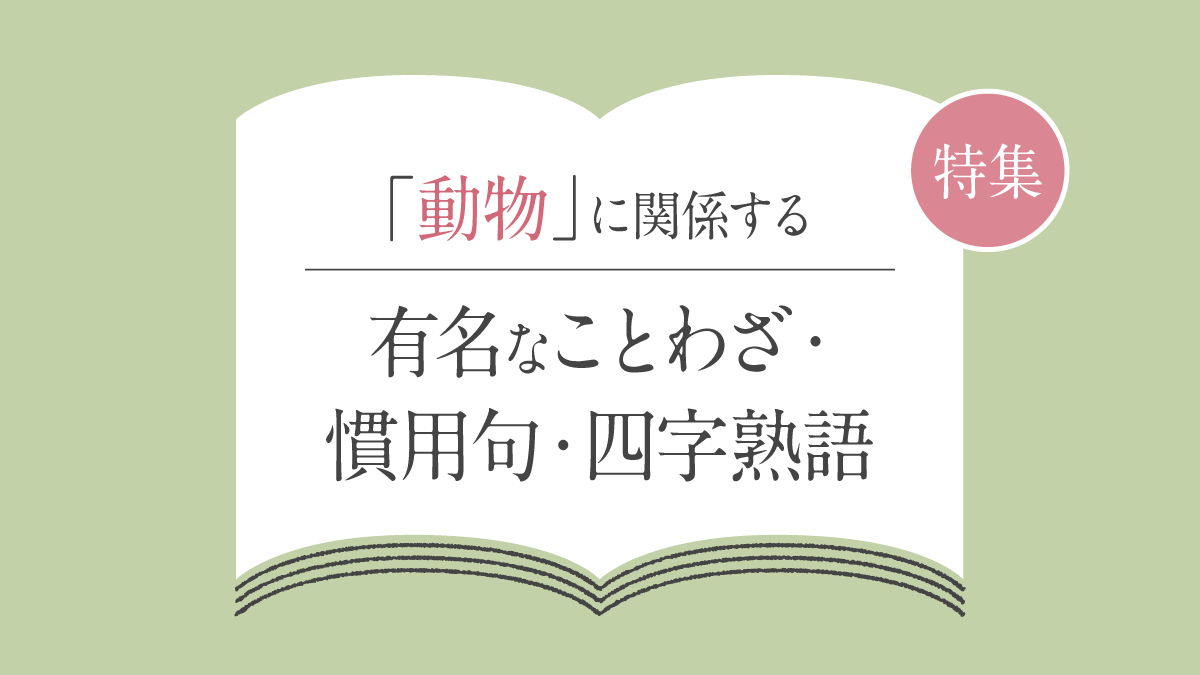
コメント