「数字」に関係する有名なことわざ・慣用句を集めてみました。
なお、こちらのページは、「数字に関係する有名なことわざ・慣用句」の一覧ページです。
「数字に関係する四字熟語」については、下記のページで詳しく解説していますので、よろしければそちらもご覧ください。
もくじ
一(いち)が入ることわざ・慣用句
- 一寸先は闇(いっすんさきはやみ)
- 意味・教訓:未来のことは誰にも予測できないということ。油断せず慎重に行動すべきという教訓を含みます。
- 使用例:「一寸先は闇だから、何が起こるか分からない。常に備えは必要だ。」
- 一事が万事(いちじがばんじ)
- 意味・教訓:一つのことを見れば、他のすべてのことを推測できるということ。細部に本質が現れるという考え方を示します。
- 使用例:「彼の服装の乱れを見ると、仕事ぶりもだらしないのではないかと思ってしまう。一事が万事と言うからね。」
- 一を聞いて十を知る(いちをきいてじゅうをしる)
- 意味・教訓:物事の一部を聞いただけで全体を理解できる、非常に賢明で察しの良いことのたとえ。
- 使用例:「彼は一を聞いて十を知るタイプだから、説明が楽だ。」
- 一石を投じる(いっせきをとうじる)
- 意味・教訓:平穏な状態にある物事に、変化や問題を提起するような行動を起こすこと。議論や反響を呼ぶきっかけとなる発言や行動を指します。
- 使用例:「彼の発言は、業界に一石を投じるものとなった。」
- 一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
- 意味・教訓:わずかな出費を惜しんだために、結果的に大きな損をしてしまうことのたとえ。目先の利益にとらわれる愚かさを戒めます。
- 使用例:「安いからといって粗悪品を買うと、すぐ壊れて結局高くつく。一文惜しみの百知らずだ。」
- 一難去ってまた一難(いちなんさってまたいちなん)
- 意味・教訓:一つの災難や困難が過ぎ去ったと思ったら、すぐにまた次の災難や困難が起こること。苦労が絶えない状況を表します。
- 使用例:「やっとトラブルが解決したと思ったら、また別の問題が発生した。まさに一難去ってまた一難だ。」
- 一か八か(いちかばちか)
- 意味・教訓:結果がどうなるか分からないが、運を天に任せて思い切ってやってみること。成功するか失敗するかわからない状況での決断や行動。
- 使用例:「成功する保証はないけれど、一か八かこの企画に挑戦してみよう。」
二(に)が入ることわざ・慣用句
- 二度あることは三度ある(にどあることはさんどある)
- 意味・教訓:同じような出来事が二度起きたら、三度目も起こりやすいということ。特に悪いことが続く場合に、注意を促すために使われます。
- 使用例:「二度あることは三度あると言うから、同じミスを繰り返さないように気をつけよう。」
- 二兎を追う者は一兎をも得ず(にとをおうものはいっとをもえず)
- 意味・教訓:同時に二つの目標を達成しようとすると、結局どちらも失敗に終わるという戒め。目標を一つに絞ることの重要性を示します。
- 使用例:「資格試験の勉強と転職活動を同時に進めていたが、結局どちらも中途半端になってしまった。二兎を追う者は一兎をも得ず、だ。」
- 二階から目薬(にかいからめぐすり)
- 意味・教訓:思うように効果が上がらないこと、遠回しすぎて役に立たないことのたとえ。もどかしい状況を表すこともあります。
- 使用例:「彼の助言はいつも抽象的で、二階から目薬だ。」
- 二の句が継げない(にのくがつげない)
- 意味・教訓:相手の言葉や状況に驚いたり呆れたりして、次の言葉が出てこない様子。
- 使用例:「あまりにも突然の知らせに、彼は二の句が継げなかった。」
- 二の足を踏む(にのあしをふむ)
- 意味・教訓:ためらって、先に進むのをためらうこと。決心がつかずに躊躇する様子。
- 使用例:「新しいプロジェクトへの参加を打診されたが、リスクを考えて二の足を踏んでいる。」
三(さん)が入ることわざ・慣用句
- 三度目の正直(さんどめのしょうじき)
- 意味・教訓:一度や二度失敗しても、三度目には成功する可能性があるということ。諦めずに挑戦し続けることの大切さを示唆します。
- 使用例:「二回連続で試験に落ちたけど、三度目の正直で今度こそ合格するぞ!」
- 三人寄れば文殊の知恵(さんにんよればもんじゅのちえ)
- 意味・教訓:平凡な人でも三人集まって相談すれば、知恵の神様である文殊菩薩のような良い考えが浮かぶものだということ。協力することの重要性を示します。
- 使用例:「この問題は難しいけど、三人寄れば文殊の知恵と言うから、みんなで解決策を考えよう。」
- 三日坊主(みっかぼうず)
- 意味・教訓:飽きっぽくて長続きしないこと、またそのような人のこと。決意が固くなく、すぐにやめてしまう様子を指します。
- 使用例:「彼は新しい趣味を始めても、いつも三日坊主で終わってしまう。」
- 仏の顔も三度まで(ほとけのかおもさんどまで)
- 意味・教訓:どんなに慈悲深い人でも、何度も無礼なことをされれば怒るということ。我慢にも限度があるという戒め。
- 使用例:「何度も同じ失敗を繰り返す彼に、上司もついに『仏の顔も三度までだぞ』と叱った。」
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
- 意味・教訓:冷たい石の上でも三年座り続ければ暖まるように、辛抱強く続ければ必ず成功するということ。忍耐の大切さを説いています。
- 使用例:「すぐに結果が出なくても、石の上にも三年というから、もう少し頑張ってみよう。」
四(し、よん)が入ることわざ・慣用句
- 四の五の言う(しのごのいう)
- 意味・教訓:あれこれと不平不満や文句を言うこと。「四の五の言わずに」の形で、言い訳などをせずに行動するよう促す際に使われます。
- 使用例:「四の五の言わずに、さっさと仕事に取り掛かれ。」
五(ご)が入ることわざ・慣用句
- 五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
- 意味・教訓:多少の違いはあっても、本質的には大差がないことのたとえ。どちらも似たようなものであるという意味合いで使われます。
- 使用例:「彼のミスも私のミスも、原因を考えれば五十歩百歩だ。」
- 五臓六腑にしみわたる(ごぞうろっぷにしみわたる)
- 意味・教訓:飲食物などが、体の隅々まで行き渡るように感じられること。特に、寒い時や疲れた時などに温かいものや美味しいものを口にした際の深い満足感を表します。
- 使用例:「寒い日に飲んだ熱いお茶が、五臓六腑にしみわたるようだった。」
六(ろく)が入ることわざ・慣用句
- 六日の菖蒲、十日の菊(むいかのあやめ、とおかのきく)
- 意味・教訓:時期に遅れて役に立たなくなってしまったもののたとえ。菖蒲は5月5日、菊は9月9日の節句に用いることから。
- 使用例:「セールが終わってから割引券を見つけても、六日の菖蒲、十日の菊だ。」
七(なな、しち)が入ることわざ・慣用句
- 七転び八起き(ななころびやおき)
- 意味・教訓:何度失敗しても、その度に屈せずに立ち上がって努力を続けることのたとえ。不屈の精神を表します。
- 使用例:「彼は事業で何度も失敗したが、七転び八起きの精神で成功を掴んだ。」
- 人の噂も七十五日(ひとのうわさもしちじゅうごにち)
- 意味・教訓:世間の噂は、長くは続かず、時が経てば自然と忘れ去られていくものだということ。
- 使用例:「今は辛いかもしれないけれど、人の噂も七十五日と言うから、あまり気にしない方がいい。」
八(はち)が入ることわざ・慣用句
- 八方美人(はっぽうびじん)
- 意味・教訓:誰に対しても愛想よく振る舞う人のこと。非難や皮肉の意味を込めて使われることが多い言葉です。
- 使用例:「彼は八方美人だから、本心がどこにあるのか分からない。」
- 八百長(やおちょう)
- 意味・教訓:前もって勝敗を決めておき、表面上は真剣に勝負しているように見せかけること。不正な談合試合などを指します。
- 使用例:「あの試合は八百長だったのではないかと疑われている。」
- 嘘八百(うそはっぴゃく)
- 意味・教訓:たくさんの嘘、または全くのでたらめのこと。「八百」は数が多いことを表します。
- 使用例:「彼が話す成功談は、どうも嘘八百のようだ。」
九(きゅう、く)が入ることわざ・慣用句
- 九死に一生を得る(きゅうしにいっしょうをえる)
- 意味・教訓:ほとんど助かる見込みのない、非常に危険な状態からかろうじて命が助かること。
- 使用例:「交通事故に遭ったが、九死に一生を得た。」
十(じゅう)が入ることわざ・慣用句
- 十人十色(じゅうにんといろ)
- 意味・教訓:人の考え方、好み、性格などは、それぞれ違っているということ。多様性を認める際に使われます。
- 使用例:「服装の好みは十人十色だから、自分の好きなものを着るのが一番だ。」
- 十把一絡げ(じっぱひとからげ)
- 意味・教訓:様々な種類や価値の異なるものを、区別せずに一つにまとめて扱うこと。大雑把な扱い方を批判的に言う場合に使うことが多いです。
- 使用例:「個性的な意見を十把一絡げにして結論を出すのは良くない。」
- 十中八九(じっちゅうはっく)
- 意味・教訓:十のうち八か九まで。ほとんど、だいたい、ほぼ確実に、という意味で使われます。
- 使用例:「これまでのデータから見て、この計画は十中八九成功するだろう。」
百(ひゃく)が入ることわざ・慣用句
- 百聞は一見に如かず(ひゃくぶんはいっけんにしかず)
- 意味・教訓:何度も人から話を聞くよりも、一度自分の目で直接見た方が確かでよく理解できるということ。実体験の重要性を示します。
- 使用例:「友人が絶賛していた景色だけど、写真では伝わらない美しさだった。やっぱり百聞は一見に如かずだね。」
- 百に一つの誤りもない(ひゃくにひとつのあやまりもない)
- 意味・教訓:まったく間違いがなく、完璧であることのたとえ。絶対的な確実性を表します。
- 使用例:「彼のデータ分析は非常に正確で、百に一つの誤りもない。」
- 可愛さ余って憎さ百倍(かわいさあまってにくさひゃくばい)
- 意味・教訓:愛情が深ければ深いほど、その愛情が裏切られたり期待外れだったりしたときの憎しみは、非常に強くなるということ。
- 使用例:「あれほど信頼していた部下に裏切られ、社長は可愛さ余って憎さ百倍だと嘆いていた。」
- 百薬の長(ひゃくやくのちょう)
- 意味・教訓:多くの薬の中で最も効果のあるもの。転じて、適量の酒はどんな薬よりも健康によいという意味で使われます。
- 使用例:「酒は百薬の長とも言うが、飲み過ぎには注意が必要だ。」
千(せん)が入ることわざ・慣用句
- 千慮の一失(せんりょのいっしつ)
- 意味・教訓:どんなに賢い人でも、多くの考えの中には一つくらいは誤りがあるものだということ。どんなに注意深く考えても、時には失敗することがある、という意味で使われます。
- 使用例:「彼の今回の判断ミスは、まさに千慮の一失だった。」
万(まん)が入ることわざ・慣用句
- 万事休す(ばんじきゅうす)
- 意味・教訓:すべての方法や手段が尽きて、もはやどうすることもできない状態になること。絶体絶命の状況を表します。
- 使用例:「財布も携帯電話も失くしてしまい、まさに万事休すだ。」
- 万全を期す(ばんぜんをきす)
- 意味・教訓:少しの抜かりもないように、十分に注意して準備すること。完璧な状態を目指して備える様子。
- 使用例:「明日のプレゼンテーションに備えて、万全を期して準備を進めている。」
- 万死に値する(ばんしにあたいする)
- 意味・教訓:何度死んでも償いきれないほど、重大な罪や過ちを犯したこと。深い反省や謝罪の気持ちを表す際に使われることがあります。
- 使用例:「取り返しのつかないミスをしてしまい、万死に値すると深く反省しております。」

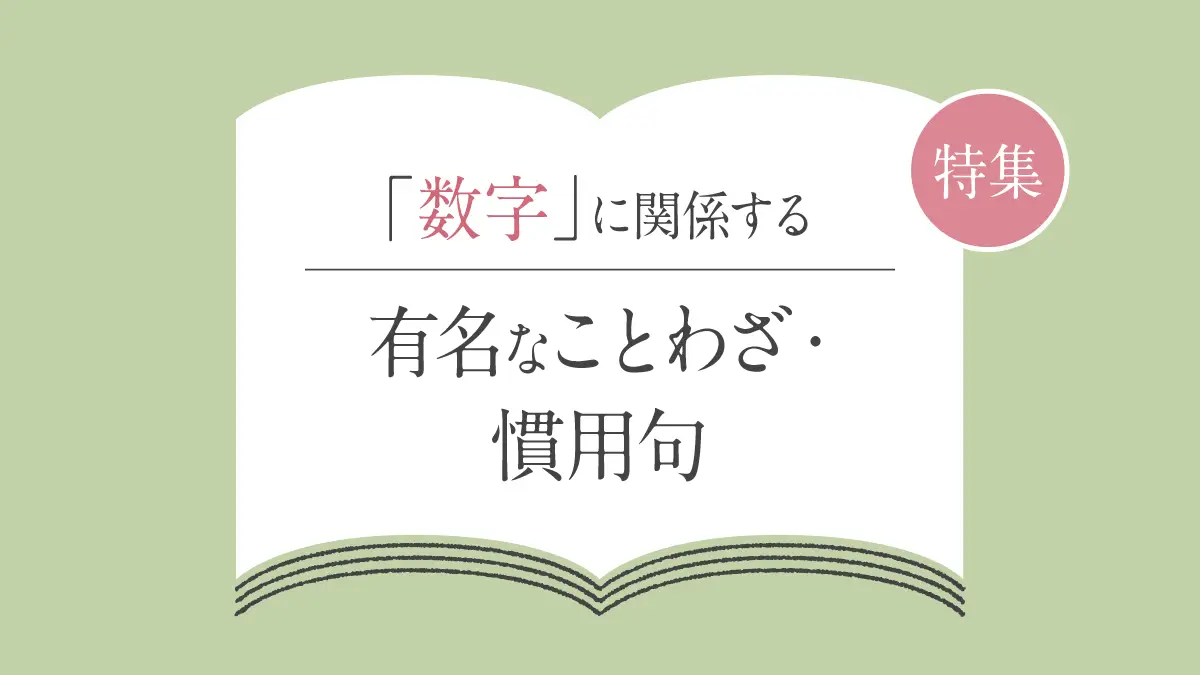
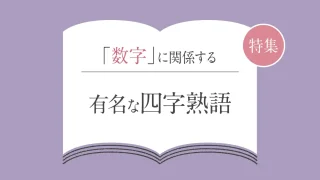
コメント