三つの漢字で構成される「三字熟語」は、私たちの言葉を豊かにしてくれる表現です。
短いながらも的確に意味を伝え、時には会話や文章に深みを与えてくれます。
よく知られる四字熟語と同じように、三字熟語にも様々な意味や由来があり、役立つ場面も多いでしょう。
もくじ
- 三字熟語と四字熟語の違い
- 有名な三字熟語 50選
- 登竜門(とうりゅうもん)
- 金字塔(きんじとう)
- 十八番(おはこ)
- 未曾有(みぞう)
- 破天荒(はてんこう)
- 間一髪(かんいっぱつ)
- 土壇場(どたんば)
- 瀬戸際(せとぎわ)
- 正念場(しょうねんば)
- 天王山(てんのうざん)
- 茶飯事(さはんじ)
- 殺風景(さっぷうけい)
- 独壇場(どくだんじょう)
- 真骨頂(しんこっちょう)
- 試金石(しきんせき)
- 太鼓判(たいこばん)
- 韋駄天(いだてん)
- 紅一点(こういってん)
- 青二才(あおにさい)
- 下馬評(げばひょう)
- 直談判(じかだんぱん)
- 赤裸裸(せきらら)
- 善後策(ぜんごさく)
- 生一本(きいっぽん)
- 音沙汰(おとさた)
- 先入観(せんにゅうかん)
- 桃源郷(とうげんきょう)
- 致命傷(ちめいしょう)
- 裸一貫(はだかいっかん)
- 分相応(ぶんそうおう)
- 不如意(ふにょい)
- 老婆心(ろうばしん)
- 野次馬(やじうま)
- 門外漢(もんがいかん)
- 守銭奴(しゅせんど)
- 五月雨(さみだれ)
- 絵空事(えそらごと)
- 有頂天(うちょうてん)
- 夢心地(ゆめごこち)
- 雪月花(せつげっか)
- 下剋上(げこくじょう)
- 金輪際(こんりんざい)
- 茶番劇(ちゃばんげき)
- 風物詩(ふうぶつし)
- 眉唾物(まゆつばもの)
- 不条理(ふじょうり)
- 別世界(べっせかい)
- 無条件(むじょうけん)
- 理不尽(りふじん)
- 臨場感(りんじょうかん)
- まとめ
三字熟語と四字熟語の違い
熟語といえば四字熟語が思い浮かべやすいですが、三字熟語とはどのような違いがあるのでしょうか。
最もわかりやすいのは文字数ですが、成り立ちや意味合いにも傾向の違いが見られます。
四字熟語は故事成語からの由来が多い一方、三字熟語は故事由来に加え、和製漢語や日常語が定着したものなど多様です。
また、四字熟語が教訓や特定の状況を示すものが多いのに対し、三字熟語は状態や性質、行為などをより直接的に表す言葉も少なくありません。
| 比較項目 | 三字熟語 | 四字熟語 |
|---|---|---|
| 文字数 | 3文字 | 4文字 |
| 成り立ち (傾向) | 故事由来、和製漢語、日常語など多様 | 故事成語由来が多い |
| 意味合い (傾向) | 状態、性質、行為などを比較的直接的に表す言葉も多い | 教訓、特定の状況、複雑な概念などを凝縮して表す言葉が多い |
有名な三字熟語 50選
登竜門(とうりゅうもん)
- 意味:立身出世や成功につながるような、突破することが難しい関門や試験のこと。
- 由来:中国の故事で、黄河の急流にある竜門という滝を登りきった鯉は竜になる、という伝説から。
- 使用例:「この賞は若手作家の登竜門と言われている。」
金字塔(きんじとう)
- 意味:後世に残る、優れた業績や功績のこと。
- 由来:エジプトのピラミッドが語源で、その壮大で永続的な姿から、不滅の偉業をたたえる言葉として使われる。
- 使用例:「彼は文学史に残る金字塔を打ち立てた。」
十八番(おはこ)
- 意味:その人が最も得意とする芸や技のこと。
- 由来:「御箱」とも書き、大切なものをしまっておく箱が語源という説や、歌舞伎役者が得意な演目を箱に入れて保管したことから、という説がある。
- 使用例:「カラオケで彼の十八番を聞かせる。」
未曾有(みぞう)
- 意味:今までに一度もなかった、非常に珍しいこと。「未だ曾(かつ)て有らず」と読み下せる。
- 由来:仏教経典などに見られる言葉が語源。
- 使用例:「未曾有の大災害が発生した。」
破天荒(はてんこう)
- 意味:今まで誰も成し遂げなかったことをすること。また、そのさま。
- 由来:中国の故事で、「天荒」は未開の地を意味し、それを打ち破ることから。本来は「前例のないこと」を成し遂げる意味合いが強い。
- 使用例:「彼の破天荒なアイデアが会社を救った。」
間一髪(かんいっぱつ)
- 意味:危険がすぐそこに迫っている、非常にあわうい状況のこと。間に髪の毛一本が入るほどのわずかな隙間、という意味。
- 使用例:「間一髪のところで衝突を避けた。」
土壇場(どたんば)
- 意味:決断や実行を迫られる、最後のぎりぎりの場面。進退きわまった状態。
- 由来:江戸時代、罪人の首を切るために土を盛って築いた場所「土壇」から。
- 使用例:「土壇場で逆転のチャンスが訪れた。」
瀬戸際(せとぎわ)
- 意味:勝敗や成否が決まる、ぎりぎりの状態や局面。
- 由来:由来は、瀬戸焼の脆さや、狭い海峡(瀬戸)などにちなむ諸説がある。
- 使用例:「交渉は決裂の瀬戸際にある。」
正念場(しょうねんば)
- 意味:その人の真価や実力が試される、最も重要な局面。ここぞという大切な場面。
- 使用例:「ここが踏ん張りどころ、まさに正念場だ。」
天王山(てんのうざん)
- 意味:勝敗や運命を左右する、極めて重要な局面。
- 由来:羽柴秀吉と明智光秀が戦った山崎の戦いにおける天王山から。
- 使用例:「この試合が優勝への天王山となる。」
茶飯事(さはんじ)
- 意味:ごくありふれていて、珍しくもない当たり前のこと。「日常茶飯事」の形で使われることが多い。
- 使用例:「彼にとって遅刻は茶飯事だ。」(※日常茶飯事の略として)
殺風景(さっぷうけい)
- 意味:趣や風情がなく、荒涼としてわびしい様子。美しい景色や、人の温かみが感じられない場所や状況に対して使われる。
- 使用例:「飾り気のない殺風景な部屋。」
独壇場(どくだんじょう)
- 意味:その人だけが思うままに活躍できる場所や場面。
- 由来:元々は「独擅場(どくせんじょう)」だが、字形や音の類似から混同され『独壇場』も広く使われる。
- 使用例:「彼のスピーチが始まると、会場は彼の独壇場となった。」
真骨頂(しんこっちょう)
- 意味:その人や物が本来持っている、最も優れた本当の姿や価値。単に「骨頂」とも言う。普段は隠れている真価が発揮されたときに使われることが多い。
- 使用例:「土壇場で逆転するとは、さすが彼の真骨頂だ。」
試金石(しきんせき)
- 意味:物の価値や人の能力・力量などを試すための出来事や機会。
- 由来:本来は、金の品質を調べるために使われた石(那智黒石など)のこと。転じて、真価を試す基準となるものを指すようになった。
- 使用例:「このプロジェクトは、彼のリーダーとしての試金石となるだろう。」
太鼓判(たいこばん)
- 意味:間違いなく確実であると保証すること。また、その保証。
- 使用例:「味は私が太鼓判を押しますので、ご安心ください。」
韋駄天(いだてん)
- 意味:足の速い神の名。転じて、足の速い人や、速く走るさま。
- 由来:仏教の守護神の一人で、仏舎利を盗んだ鬼を追いかけて取り戻したという俗説から。
- 使用例:「彼は韋駄天のように走り去った。」
紅一点(こういってん)
- 意味:多くの男性の中に、ただ一人だけ女性がいること。
- 由来:暗い背景の中に一つだけ赤い花が咲いている様子にたとえた言葉。
- 使用例:「会議の出席者は男性ばかりで、彼女が紅一点だった。」
青二才(あおにさい)
- 意味:年齢が若く、経験が未熟な人のこと。特に男性に対して使われることが多い。
- 由来:由来は魚や馬の年齢(二才)などにちなむとされる。「青」は未熟さを表す。
- 使用例:「まだまだ青二才ですが、精一杯頑張ります。」
下馬評(げばひょう)
- 意味:世間の人々が、当事者以外で無責任にする噂や評判のこと。
- 由来:昔、城や屋敷の門前で、馬から降りた供の者たちが主人を待つ間に交わした噂話が語源とされている。
- 使用例:「下馬評では、Aチームが有利とされている。」
直談判(じかだんぱん)
- 意味:間に人を立てず、直接相手と話し合って交渉や依頼をすること。重要な要件や、込み入った話をするときなどに用いられる。
- 使用例:「社長に給与アップを直談判する。」
赤裸裸(せきらら)
- 意味:何も隠すところがなく、すべてをさらけ出している様子。ありのまま、むき出しの状態を表す。
- 使用例:「彼は自分の過去を赤裸裸に語った。」
善後策(ぜんごさく)
- 意味:起きてしまった問題や失敗をうまく処理し、事態を収拾するための方法や手段。事後の対応策という意味合いが強い。
- 使用例:「不祥事のあと、会社は信頼回復のための善後策を講じた。」
生一本(きいっぽん)
- 意味:混じりけがなく純粋なこと。また、一途でひたむきな性質や性格のこと。
- 由来:本来は、醸造したままで水などを加えていない日本酒を指す言葉だった。
- 使用例:「彼は嘘のつけない生一本な性格だ。」
音沙汰(おとさた)
- 意味:便りや連絡、様子の知らせのこと。多くの場合、「音沙汰がない」のように打ち消しの形で使われ、連絡が途絶えている状態を表す。
- 使用例:「卒業してから、彼からは何の音沙汰もない。」
先入観(せんにゅうかん)
- 意味:最初に得た情報や知識によって、固定的に抱いてしまう見方や考え方。偏見や思い込みとほぼ同じ意味で使われる。
- 使用例:「先入観を持たずに、公平に判断することが大切だ。」
桃源郷(とうげんきょう)
- 意味:俗世間を離れた、平和で美しい理想の世界。ユートピア。
- 由来:中国の詩人、陶淵明(とうえんめい)の『桃花源記(とうかげんき)』という作品に出てくる、桃の花が咲き乱れる理想郷が由来。
- 使用例:「都会の喧騒を離れ、まるで桃源郷のような村にたどり着いた。」
致命傷(ちめいしょう)
- 意味:命に関わるような、非常に重い傷のこと。転じて、再起不能になるほどの大きな打撃や失敗を指す場合もある。
- 使用例:「その一言が、二人の関係にとって致命傷となった。」
裸一貫(はだかいっかん)
- 意味:自分の体以外には何も財産を持たないこと。何も頼るものがなく、自分の力だけで物事を始める状況を指す。
- 使用例:「彼は裸一貫から身を起こし、大企業を築いた。」
分相応(ぶんそうおう)
- 意味:その人の身分や能力、財産などにふさわしいこと。自分の置かれた状況や立場に合った言動や生活をすることを表す。
- 使用例:「あまり贅沢せず、分相応の暮らしを心がけている。」
不如意(ふにょい)
- 意味:思い通りにならないこと。特に、経済的に苦しい状態を指すことが多い。「意の如(ごと)くならず」という意味。
- 使用例:「近頃、少々不如意で困っている。」
老婆心(ろうばしん)
- 意味:必要以上に気を遣い、世話を焼いたり心配したりすること。度を越した親切心や、忠告などを謙遜して言う場合に使う。
- 使用例:「老婆心ながら申し上げますが、もう少し慎重になった方がよろしいかと存じます。」
野次馬(やじうま)
- 意味:自分とは直接関係のない出来事に、興味本位で集まったり騒ぎ立てたりする人のこと。
- 由来:語源は老いた馬(親馬)や弥次郎兵衛(やじろべえ)などに由来する諸説がある。
- 使用例:「事故現場には大勢の野次馬が集まっていた。」
門外漢(もんがいかん)
- 意味:その分野について専門家でない人。畑違いの人。素人。専門的な知識や経験がないことを示す。
- 使用例:「医学については門外漢なので、詳しいことは分かりません。」
守銭奴(しゅせんど)
- 意味:お金を貯め込むことばかりに執着し、使うことを極端に嫌う人のこと。けちで欲深い人を非難する意味で使われる。
- 使用例:「彼は近所でも有名な守銭奴だ。」
五月雨(さみだれ)
- 意味:梅雨のころに降り続く雨。転じて、物事が断続的にだらだらと続くことのたとえ。
- 使用例:「質問が五月雨式に寄せられた。」
絵空事(えそらごと)
- 意味:現実にはありえない、大げさな話や計画。実現性のないこと。
- 使用例:「彼の壮大な計画は、絵空事に過ぎなかった。」
有頂天(うちょうてん)
- 意味:喜びや得意のあまり、我を忘れて舞い上がっている状態。
- 由来:仏教で、迷いの世界(欲界、色界、無色界)の中で最も高い天である「有頂天」から。
- 使用例:「試験に合格して有頂天になっている。」
夢心地(ゆめごこち)
- 意味:まるで夢を見ているかのような、ぼんやりとして心地よい気分。
- 使用例:「温泉にゆっくり浸かって夢心地になった。」
雪月花(せつげっか)
- 意味:日本の四季の美しい自然の景物(冬の雪、秋の月、春の花)。風流なものの代表。
- 使用例:「雪月花をめでる。」
下剋上(げこくじょう)
- 意味:地位が下の者が上の者を倒して権力を握ること。
- 由来:主に日本の戦国時代に見られた社会風潮を指す歴史用語。
- 使用例:「戦国時代の下剋上の世。」
金輪際(こんりんざい)
- 意味:(下に打ち消しを伴い)決して。絶対に。
- 由来:仏教で、大地が載っているとされる最下層の「金輪」の、さらに底の果てを意味する言葉から。
- 使用例:「金輪際、嘘はつきません。」
茶番劇(ちゃばんげき)
- 意味:見え透いた、ばかばかしい出来事。まじめに取り合う価値のない、ふざけた騒ぎ。
- 使用例:「彼らの言い争いは、まるで茶番劇だ。」
風物詩(ふうぶつし)
- 意味:その季節ならではの感じを与えるもの。その季節の情景をよく表している事物。
- 使用例:「花火は夏の風物詩だ。」
眉唾物(まゆつばもの)
- 意味:真偽が疑わしく、信用できない話や物。
- 由来:眉に唾をつけると狐などに化かされないという俗信から。
- 使用例:「その儲け話は眉唾物だ。」
不条理(ふじょうり)
- 意味:道理に合わないこと。筋が通らないこと。わけのわからないこと。
- 使用例:「不条理な要求に憤りを感じる。」
別世界(べっせかい)
- 意味:現実とはかけ離れた、全く違う世界や場所。また、そのような雰囲気。
- 使用例:「一歩足を踏み入れると、そこは別世界だった。」
無条件(むじょうけん)
- 意味:条件を一切つけないこと。
- 使用例:「彼の提案を無条件で受け入れる。」
理不尽(りふじん)
- 意味:道理に合わないこと。筋道の通らないこと。また、そのさま。
- 使用例:「理不尽な扱いに耐えられない。」
臨場感(りんじょうかん)
- 意味:実際にその場にいるかのような感じ。リアルな感覚。
- 使用例:「VRゴーグルで臨場感あふれる映像を楽しむ。」
まとめ
最後に、この記事で紹介した三字熟語を、実際の会話や文章で効果的に使うためのヒントをいくつかご紹介します。
- 意味を正確に理解する
まずは、言葉の意味を正しく把握することが大切です。
似たような言葉とのニュアンスの違いを知っておくと、より的確な表現ができます。
意味が曖昧なまま使うと、誤解を招く可能性もあります。 - 使う場面(TPO)を考える
三字熟語の中には、少し硬い響きを持つものもあります。
友人との気軽な会話で使うのか、改まった文章で使うのかなど、時・場所・相手(場面)に合わせて使い分けることを意識しましょう。 - 文脈に馴染ませる
言葉だけが浮いてしまわないよう、前後の文脈に自然に溶け込むように使うことがポイントです。
急に難しい言葉を入れるのではなく、話の流れの中でスムーズに使えると良いでしょう。 - 使いすぎに注意する
便利な三字熟語ですが、一つの文章や会話の中で多用しすぎると、かえって読みにくくなったり、くどい印象を与えたりすることがあります。
ここぞという場面で効果的に使うのがおすすめです。 - 迷ったら辞書などで確認を
少しでも使い方に不安を感じたら、辞書等で意味や用法、例文を確認する習慣をつけましょう。
正しい使い方を積み重ねることが、表現力アップにつながります。
これらのヒントを参考に、ぜひ三字熟語を使いこなし、ご自身の表現の幅を広げてみてください。

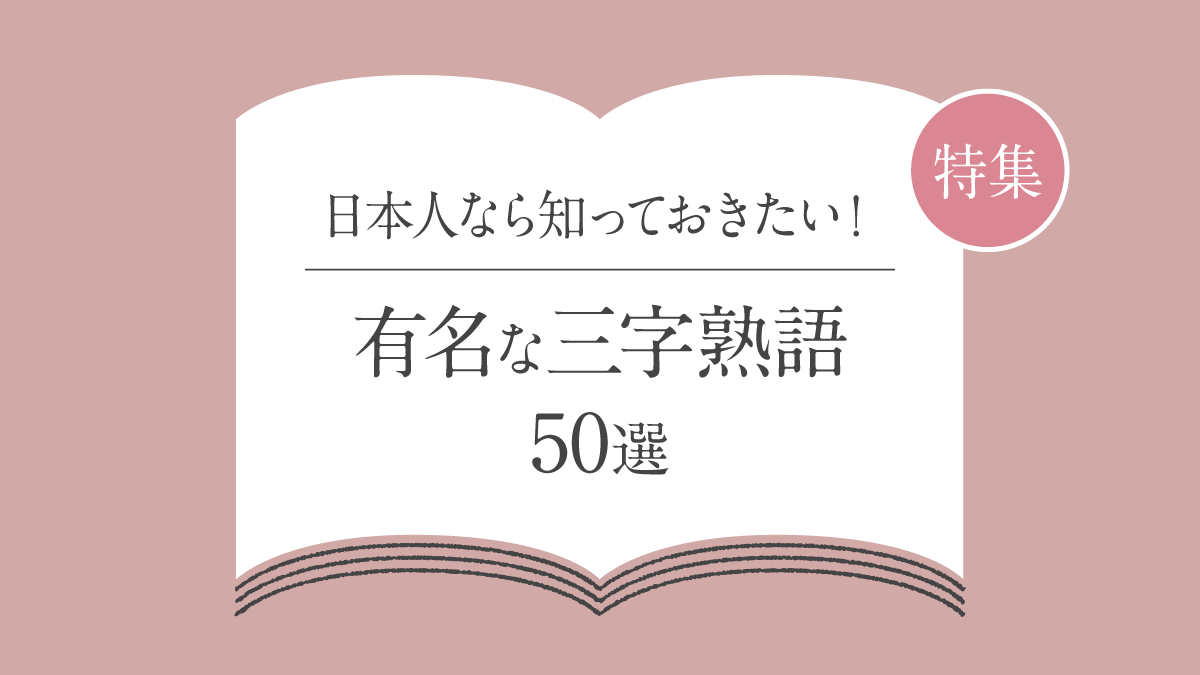

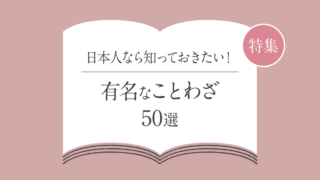
コメント