
鳥に関することわざ・慣用句一覧
- 鶴の一声(つるのひとこえ):
有力者の一言で、多くの人の意見や状況がすぐに変わることのたとえ。 - 雀の涙(すずめのなみだ):
ごくわずかなもののたとえ。 - 鵜のまねをする烏(うのまねをするからす):
自分の能力を考えずに、人の真似をして失敗することのたとえ。 - 鳶が鷹を生む(とびがたかをうむ):
平凡な親から優れた子供が生まれることのたとえ。 - 閑古鳥が鳴く(かんこどりがなく):
人が来なくて寂れている様子。商売がはやらないことのたとえ。 - 立つ鳥跡を濁さず(たつとりあとをにごさず):
立ち去る者は、後始末をきちんとすべきであることのたとえ。 - 烏合の衆(うごうのしゅう):
規律や統制のない群衆のこと。 - 焼け野の雉子、夜の鶴(やけののきぎす、よるのつる):
親が子を思う情愛が非常に深いことのたとえ - 卵を見て時夜を求む(たまごをみてじやをもとむ):
早合点すること。時期尚早なことのたとえ。 - 鴨が葱を背負って来る(かもがねぎをしょってくる):
うまいことが重なり、ますます好都合であること。 - 燕雀安くんぞ鴻鵠の志を知らんや(えんじゃくいずくんぞこうこくのこころざしをしらんや):
小人物には大人物の考えは理解できないことのたとえ。 - 鵜の目鷹の目(うのめたかのめ):
鋭い目つきで物を探し出す様子。 - 雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず):
幼い頃に覚えたことは、年老いても忘れないことのたとえ。 - 窮鳥懐に入れば猟師も殺さず (きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず): 助けを求めてきたものは、敵であっても助けるべきというたとえ
- 鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん(にわとりをさくにいずくんぞぎゅうとうをもちいん):
小さなことを処理するのに大げさな手段は必要ないことのたとえ。 - 大鳥の尾より小鳥の頭(おおどりのおよりことりのあたま):
大きな組織で下位にいるより、小さな組織でトップに立つほうがよいという意味。「鯛の尾より鰯の頭」のより古い言い回し。 - 雉も鳴かずば撃たれまい(きじもなかずばうたれまい):
余計なことを言わなければ災いを招かないで済むことのたとえ。 - 欲の熊鷹股を裂く(よくのくまたかまたをさく):
欲が深すぎるとそのためにわざわいを招くことになるというたとえ。 - 群鶏の一鶴(ぐんけいのいっかく):
多くの平凡なものの中に、一つだけ特に優れたものが混じっていることのたとえ。 - 掃き溜めに鶴(はきだめにつる):汚い場所に、場違いなほど美しく優れたものが現れることのたとえ。

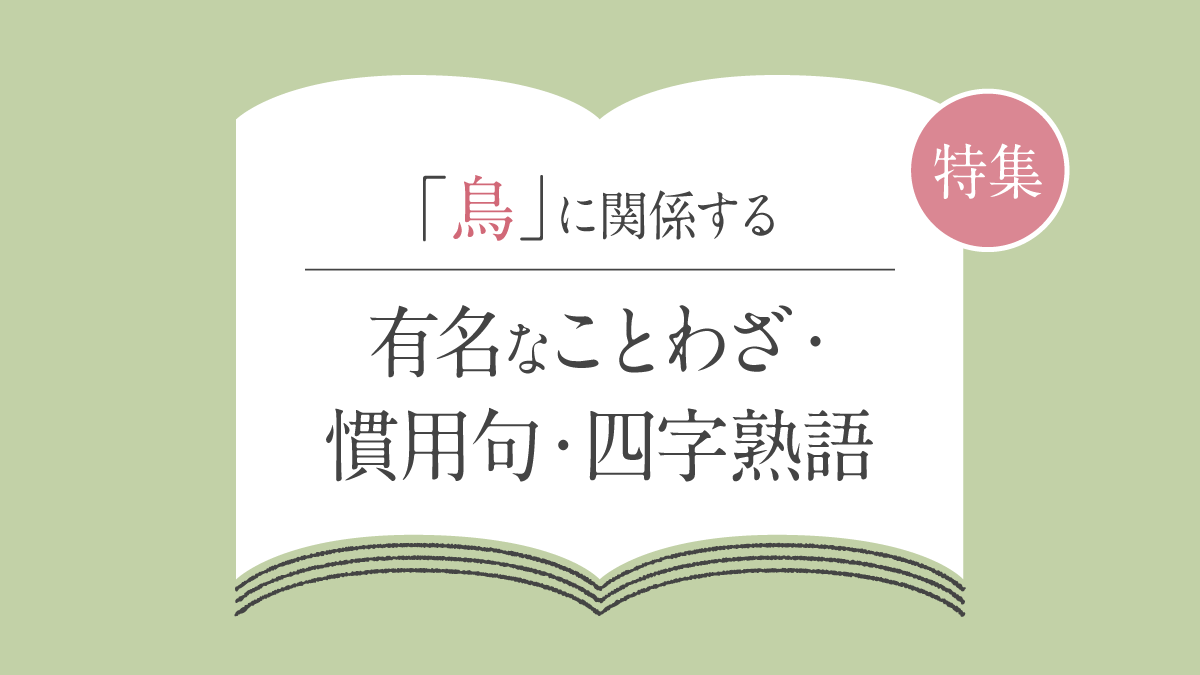
コメント