私たちの体の一部を使った言葉は、日常会話の中に驚くほどたくさん存在します。
感情、状態、行動などを表現する際に、体の部位を比喩的に使うことで、より具体的で生き生きとした表現になるからです。
この記事では、頭のてっぺんからつま先まで、体の様々な部位を使ったことわざ・慣用句・四字熟語を、部位ごとにまとめてご紹介します。
もくじ
1. 頭
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 頭隠して尻隠さず (あたまかくしてしりかくさず) | 欠点の一部を隠しただけで、全部隠せていないこと。 |
| 頭が上がらない (あたまがあがらない) | 相手に引け目を感じて、対等な態度がとれないこと。 |
| 頭を冷やす (あたまをひやす) | 冷静になること。 |
| 頭を丸める (あたまをまるめる) | 出家すること、または反省して俗世を捨てること。 |
| 頭から水を浴びたよう (あたまからみずをあびたよう) | 突然の出来事に驚き、呆然とすること。 |
| 頭ごなし (あたまごなし) | 相手の意見を聞かず、一方的に押さえつけること。 |
| 頭角を現す (とうかくをあらわす) | 才能や力量が人より抜きんでてくること。 |
| 頭押さえりゃ尻上がる (あたまおさえりゃしりあがる) | ある問題を解決しようとすると、別の問題が生じることのたとえ。 |
| 頭脳明晰 (ずのうめいせき) | 頭の働きが非常に優れていること。 |
2. 顔
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 顔が広い (かおがひろい) | 多くの人と知り合いであること。 |
| 顔を立てる (かおをたてる) | 相手の面目を保つこと。 |
| 顔に泥を塗る (かおにどろをぬる) | 相手の名誉を傷つけること。 |
| 顔から火が出る (かおからひがでる) | 非常に恥ずかしい思いをすること。 |
| 顔を出す (かおをだす) | ある場所に姿を見せること。 |
| 合わせる顔がない (あわせるかおがない) | 相手に申し訳なくて会えないこと。 |
| 涼しい顔 (すずしいかお) | 平然としていること。 |
| 知らぬ顔の半兵衛 (しらぬかおのはんべえ) | 知らないふりをすること。 |
3. 目
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 目から鱗が落ちる (めからうろこがおちる) | あることがきっかけで、急に物事の本質がわかるようになること。 |
| 目から鼻へ抜ける (めからはなへぬける) | 非常に賢いこと。 |
| 目に入れても痛くない (めにいれてもいたくない) | 非常に可愛がること。 |
| 目くじらを立てる (めくじらをたてる) | 些細なことに怒ること。 |
| 目を疑う (めをうたがう) | 信じられないような光景を見ること。 |
| 目をかける (めをかける) | 特に目を留めて、面倒を見ること。 |
| 目を盗む (めをぬすむ) | 人の見ていないところで、こっそり何かをすること。 |
| 目を光らせる (めをひからせる) | 厳しく監視すること。 |
| 目を見張る (めをみはる) | 驚いて目を大きく開くこと。 |
| 目の上の瘤 (めのうえのこぶ) | 邪魔で目障りな存在。 |
| 目の色を変える (めのいろをかえる) | 真剣になったり、怒ったりして表情が変わること。 |
| 目と鼻の先 (めとはなのさき) | 非常に近い距離。 |
| 長い目で見る (ながいめでみる) | 気長に将来を見守ること。 |
| 目は口ほどに物を言う (めはくちほどにものをいう) | 情をこめた目つきは、口で話す以上に強く相手の心を捉える。 |
| 白眼視 (はくがんし) | 冷たい目で見ること。 |
| 眼光紙背に徹す (がんこうしはいにてっす) | 書物の奥深い意味まで理解すること。 |
4. 鼻
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 鼻が高い (はながたかい) | 得意であること、誇らしいこと。 |
| 鼻であしらう (はなであしらう) | 冷淡な態度で相手をすること。 |
| 鼻にかける (はなにかける) | 自慢すること。 |
| 鼻につく (はなにつく) | 嫌な感じがして、飽き飽きすること。 |
| 鼻を明かす (はなをあかす) | 出し抜いて驚かせること。 |
| 鼻を折る (はなをおる) | 相手の慢心をくじくこと。 |
| 鼻の下が長い (はなのしたがながい) | だらしがない様子 |
| 鼻持ちならない (はなもちならない) | 相手の言動が見え透いていて、我慢できないほど不快なさま。 |
5. 口・唇
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 口がうまい (くちがうまい) | 話すことが巧みであること。 |
| 口が堅い (くちがかたい) | 秘密を守ること。 |
| 口が軽い (くちがかるい) | 秘密をすぐに人に話してしまうこと。 |
| 口が滑る (くちがすべる) | うっかり言ってはいけないことを言ってしまうこと。 |
| 口が減らない (くちがへらない) | 負け惜しみを言うこと。 |
| 口に合う (くちにあう) | 飲食物が自分の好みに合うこと。 |
| 口にする (くちにする) | 食べること、または言うこと。 |
| 口を出す (くちをだす) | 余計な口出しをすること。 |
| 口を噤む (くちをつぐむ) | 黙ること。 |
| 口を切る (くちをきる) | 最初に発言すること。 |
| 口を割る (くちをわる) | 白状すること。 |
| 口八丁手八丁 (くちはっちょうてはっちょう) | 話すこともすることも達者なこと。 |
| 唇を噛む (くちびるをかむ) | 悔しさや怒りをこらえること。 |
| 目は口ほどに物を言う (めはくちほどにものをいう) | 情をこめた目つきは、口で話す以上に強く相手の心を捉える。 |
| 唇亡びて歯寒し (くちびるほろびてはさむし) | 助け合うものが滅びると、自分も危うくなること。 |
| 巧言令色 (こうげんれいしょく) | 言葉巧みで、表情を取り繕うこと。 |
6. 歯
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 歯が浮く (はがうく) | 軽薄な言動を見聞きして不快になること。 |
| 歯が立たない (はがたたない) | 相手が強すぎてかなわないこと。 |
| 歯に衣着せぬ (はにきぬきせぬ) | 遠慮せず、思ったままを言うこと。 |
| 歯を食いしばる (はをくいしばる) | 苦痛や悔しさを我慢すること。 |
| 奥歯に物が挟まったよう (おくばにものがはさまったよう) | はっきりと言わない、思わせぶりな言い方。 |
7. 舌
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 舌が回る (したをまわる) | 滑らかに話すこと。 |
| 舌鼓を打つ (したつづみをうつ) | 美味しそうに食べること。 |
| 舌先三寸 (したさきさんずん) | 口先だけでうまく人をあしらうこと。 |
| 舌を巻く (したをまく) | 非常に驚き感心すること。 |
| 二枚舌を使う (にまいじたをつかう) | 矛盾したことを言うこと、嘘をつくこと。 |
8. 耳
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 耳が痛い (みみがいたい) | 自分の弱点を指摘されて、つらいこと。 |
| 耳が早い (みみがはやい) | 情報を聞きつけるのが早いこと。 |
| 耳にたこができる (みみにたこができる) | 同じことを何度も聞かされて、うんざりすること。 |
| 耳にする (みみにする) | 聞くこと。 |
| 耳を疑う (みみをうたがう) | 聞いたことが信じられないこと。 |
| 耳を貸す (みみをかす) | 相談に乗ったり、話を聞いたりすること。 |
| 耳を澄ます (みみをすます) | 注意して聞くこと。 |
| 耳を揃える (みみをそろえる) | 必要な金銭をきちんと用意すること。 |
| 寝耳に水 (ねみみにみず) | 思いがけない出来事に驚くこと。 |
| 小耳に挟む (こみみにはさむ) | ちらっと聞くこと。 |
9. 首
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 首が回らない (くびがまわらない) | 借金などで、やりくりがつかないこと。 |
| 首を長くする (くびをながくする) | 待ち焦がれること。 |
| 首を突っ込む (くびをつっこむ) | あることに深入りすること。 |
| 首をひねる (くびをひねる) | 疑わしく思うこと。 |
| 首を縦に振る (くびをたてにふる) | 承知すること。 |
| 首を切る (くびをきる) | 解雇すること。 |
| 首の皮一枚 (くびのかわいちまい) | かろうじてつながっている状態。 |
10. 肩
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 肩で風を切る (かたでかぜをきる) | 得意げに、威張って歩くこと。 |
| 肩の荷が下りる (かたのにがおりる) | 責任や負担から解放されること。 |
| 肩を並べる (かたをならべる) | 対等な地位にいること。 |
| 肩を持つ (かたをもつ) | 味方すること。 |
| 肩を落とす (かたをおとす) | がっかりすること。 |
| 肩を入れる (かたをいれる) | ひいきすること |
11. 胸
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 胸が痛む (むねがいたむ) | 心配や悲しみで心が痛むこと。 |
| 胸が騒ぐ (むねがさわぐ) | 良くない予感がすること。 |
| 胸がすく (むねがすく) | 気持ちが晴れやかになること。 |
| 胸が詰まる (むねがつまる) | 悲しみや感激でいっぱいになること。 |
| 胸を打つ (むねをうつ) | 感動させること。 |
| 胸を張る (むねをはる) | 自信に満ちていること。 |
| 胸を躍らせる (むねをおどらせる) | 期待や喜びでわくわくすること。 |
| 胸に手を当てる (むねにてをあてる) | 深く考えること |
12. 手
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 手が出ない (てがでない) | 高価で買えないこと、または能力が及ばないこと。 |
| 手が出せない (てがだせない) | 高価で買えないこと、能力不足で対応できないこと、または、怖くて手出しできないこと。 |
| 手がかかる (てがかかる) | 世話が焼けること。 |
| 手が空く (てがあく) | 仕事に余裕ができること。 |
| 手が足りない (てがたりない) | 人手が不足していること。 |
| 手が早い (てがはやい) | 動作が素早いこと、すぐに異性に手を出すこと。 |
| 手塩にかける (てしおにかける) | 大切に育てること。 |
| 手に汗握る (てにあせにぎる) | はらはらどきどきすること。 |
| 手に負えない (てにおえない) | 自分の力ではどうにもできないこと。 |
| 手も足も出ない (てもあしもでない) | どうすることもできないこと。 |
| 手に乗る (てにのる) | 相手の計略にはまること。 |
| 手を打つ (てをうつ) | 対策を講じること、または合意すること。 |
| 手を貸す (てをかす) | 協力すること。 |
| 手を切る (てをきる) | 関係を断つこと。 |
| 手を尽くす (てをつくす) | あらゆる手段を試みること。 |
| 手を抜く (てをぬく) | いい加減にすること。 |
| 手を広げる (てをひろげる) | 事業などを拡大すること。 |
| 手を焼く (てをやく) | 扱いに困ること。 |
| 手を差し伸べる (てをさしのべる) | 困っている人などに救いの手を与えること。 |
| 悪事千里を走る (あくじせんりをはしる) | 悪い行いはすぐに世間に知れ渡ること。 |
| 濡れ手で粟 (ぬれてであわ) | 苦労せずに利益を得ること。 |
| 手をこまねく (てをこまねく) | 何もしないで見ていること。 |
| 拱手傍観 (きょうしゅぼうかん) | 何もしないで見ていること。 |
13. 指
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 指をくわえる (ゆびをくわえる) | うらやましそうに見ていること。 |
| 指をさす (ゆびをさす) | 非難すること。 |
| 指折り数える (ゆびおりかぞえる) | 楽しみに待つこと。 |
14. 爪
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 爪が長い (つめがながい) | 欲深いこと。 |
| 爪に火をともす (つめにひをともす) | 非常に倹約すること。 |
| 爪の垢ほど (つめのあかほど) | ごくわずかな量。 |
| 爪の垢を煎じて飲む (つめのあかをせんじてのむ) | 優れた人に少しでもあやかろうとすること。 |
15. 腹
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 腹が黒い (はらがくろい) | 心に悪巧みがあること。 |
| 腹が立つ (はらがたつ) | 怒ること。 |
| 腹が太い (はらがふとい) | 度胸があること。 |
| 腹が煮えくり返る (はらがにえくりかえる) | 激しく怒ること。 |
| 腹を抱える (はらをかかえる) | おかしくてたまらないこと。 |
| 腹を割る (はらをわる) | 正直に話すこと。 |
| 腹を決める (はらをきめる) | 覚悟すること。 |
| 腹をくくる (はらをくくる) | 覚悟すること。 |
| 腹を探る (はらをさぐる) | 相手の考えを知ろうとすること。 |
| 自腹を切る (じばらをきる) | 自分で費用を負担すること。 |
| 太っ腹 (ふとっぱら) | 度量が大きいこと。 |
16. ヘソ
17. 腰
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 腰が低い (こしがひくい) | 人に謙虚な態度で接すること。 |
| 腰が抜ける (こしがぬける) | 驚いて立てなくなること。 |
| 腰を据える (こしをすえる) | 落ち着いて物事に取り組むこと。 |
| 腰を抜かす (こしをぬかす) | 非常に驚くこと。 |
| 腰を折る (こしをおる) | 人の話の邪魔をすること。 |
| 腰を据える (こしをすえる) | 落ち着いて物事に取り組むこと |
18. お尻
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 尻が重い (しりがおもい) | なかなか行動を起こさないこと。 |
| 尻が軽い (しりがかるい) | 軽々しく行動すること。 |
| 尻に火がつく (しりにひがつく) | 切羽詰まって慌てること。 |
| 尻に敷く (しりにしく) | 妻や部下などを、自分の思うままにすること。 |
| 尻を叩く (しりをたたく) | 励ますこと、促すこと。 |
| 尻を持ち込む (しりをもちこむ) | 面倒なことを持ち込むこと |
| 頭押さえりゃ尻上がる (あたまおさえりゃしりあがる) | ある問題を解決しようとすると、別の問題が生じることのたとえ。 |
19. 足
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 足が出る (あしがでる) | 予算を超えること。 |
| 足が早い (あしがはやい) | 食べ物が腐りやすいこと、または、歩くのが速いこと。 |
| 足が棒になる (あしがぼうになる) | 歩き疲れて足がこわばること。 |
| 足下を見る (あしもとをみる) | 相手の弱みにつけこむこと。 |
| 足を洗う (あしをあらう) | 良くないことをやめること。 |
| 足を引っ張る (あしをひっぱる) | 人の成功や前進の邪魔をすること。 |
| 足を運ぶ (あしをはこぶ) | 出向くこと。 |
| 足蹴にする (あしげにする) | ひどい扱いをすること。 |
| 二足の草鞋を履く (にそくのわらじをはく) | 二つの職業を兼ねること。 |
| 健脚を誇る (けんきゃくをほこる) | 足が丈夫であること |
20. 骨
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 骨が折れる (ほねがおれる) | 苦労が多いこと。 |
| 骨身を惜しまない (ほねみをおしまない) | 苦労をいとわないこと。 |
| 骨身を削る (ほねみをけずる) | 非常に苦労すること。 |
| 骨までしゃぶる (ほねまでしゃぶる) | 徹底的に利用しつくすこと。 |
21. 血
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 血が騒ぐ (ちがさわぐ) | 興奮すること。 |
| 血で血を洗う (ちでちをあらう) | 殺傷が続くこと |
| 血の気が多い (ちのけがおおい) | 感情的になりやすいこと |
| 血も涙もない (ちもなみだもない) | 人間味がないこと。 |
| 血が上る (ちがのぼる) | かっとなること |
| 血を分ける (ちをわける) | 親子、兄弟など血縁関係がある |
22. その他(全身・複数の部位)
| ことわざ・慣用句 | 意味 |
|---|---|
| 身から出た錆 (みからでたさび) | 自分の犯した過ちが原因で、苦しい立場になること。 |
| 身に染みる (みにしみる) | 深く感じること。 |
| 身の毛がよだつ (みのけがよだつ) | 非常に恐ろしいこと。 |
| 身の程知らず (みのほどしらず) | 自分の能力をわきまえないこと。 |
| 身を粉にする (みをこにする) | 一生懸命に働くこと。 |
| 身を固める (みをかためる) | 結婚すること、または、職業に就いて生計を立てること。 |
| 身を立てる (みをたてる) | 世間から認められるようになること。 |
| 五臓六腑にしみわたる (ごぞうろっぷにしみわたる) | 体全体に深くしみ込むこと。 |
| 全身全霊 (ぜんしんぜんれい) | 体と心のすべて。 |
| 身体髪膚,之を父母に受く (しんたいはっぷこれをごふぼにうく) | 体はすべて父母からいただいたものであるから、大切にしなければならないということ。 |
| 名は体を表す (なはたいをあらわす) | 名前はそのものの性質や実体をよく表している。 |
まとめ
体の一部を使ったことわざ・慣用句・四字熟語は、日本語の表現力を豊かにする、重要な要素です。
これらの言葉を適切に使うことで、会話や文章がより生き生きとし、相手に伝えたいことがより深く伝わるようになるでしょう。
ぜひ、日常生活の中で意識して使ってみてください。

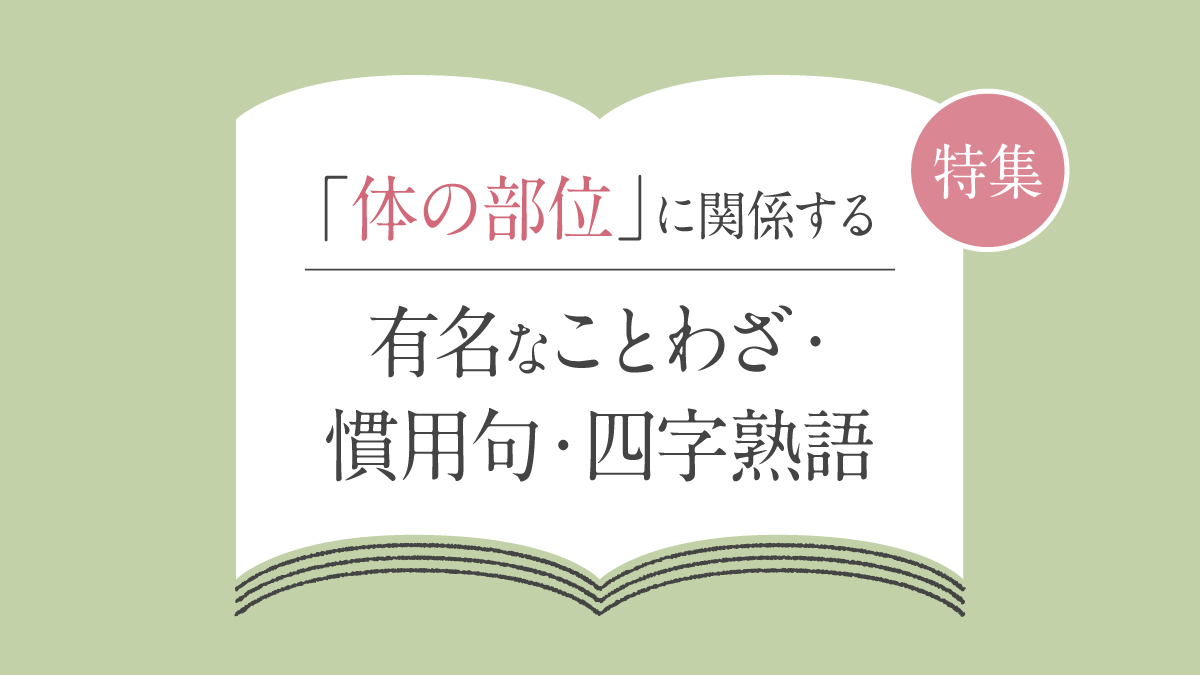
コメント