日本は四季がはっきりしており、それぞれの季節には美しい風景や、特徴的な気候、行事があります。
古くから、人々は季節の移り変わりを敏感に感じ取り、それをことわざや慣用句、そして四字熟語として表現してきました。
これらの言葉は、単に季節を表すだけでなく、人生の教訓や、人々の暮らしの知恵を含んでいることもあります。
この記事では、季節に関係する有名なことわざ・慣用句、そして四字熟語を、四季ごとにまとめてご紹介します。
もくじ
「春」のことわざ・慣用句、故事成語、四字熟語
春は、暖かくなり、生命が芽吹く季節。希望や始まりを感じさせる言葉があります。

「春」のことわざ・慣用句
- 暑さ寒さも彼岸まで(あつささむさもひがんまで):
春の彼岸(春分の日前後)になれば冬の寒さが和らぎ、秋の彼岸(秋分の日前後)になれば夏の暑さも衰えるということ。季節の移り変わりの目安。 - 春の雪と叔母の杖は怖くない(はるのゆきとおばのつえはこわくない):
春の雪はすぐに消え、叔母(または老女)が振り上げる杖も本気ではないことから、見かけは恐ろしそうでも、実際には大したことのないもののたとえ。 - 春一番(はるいちばん):
立春から春分の間に、その年初めて吹く強い南風。本格的な春の訪れを告げる風とされる。 - 花冷え(はなびえ):
桜の花が咲く頃に、一時的に寒さがぶり返すこと。また、その寒さ。 - 朧月夜(おぼろづきよ):
春の夜、月が霞(かすみ)や靄(もや)などによって、ぼんやりと柔らかく見える様子。春の夜の情趣を表す言葉。 - 春はあけぼの(はるはあけぼの):
清少納言『枕草子』の有名な冒頭。「春は夜明け方が最も趣深い」という意味。春の情景を代表する表現。
「春」の故事成語
- 春眠暁を覚えず(しゅんみんあかつきをおぼえず):
唐の詩人、孟浩然の詩「春暁」の一節。春の夜はまことに眠り心地がよく、朝が来たことにも気づかないほど熟睡してしまうこと。 - 春宵一刻値千金(しゅんしょういっこくあたいせんきん):
宋の詩人、蘇軾の詩「春夜」の一節。春の夜は趣深く風情があり、そのほんのわずかな時間(一刻)にも千金ほどの価値があるということ。 - 柳緑花紅(りゅうりょくかこう):
「柳は緑色、花は紅色」と、春の美しい景色そのものを描写した言葉。転じて、自然のあるがままの姿や、当然の道理を指すこともある。(禅語に由来)
「春」の四字熟語
- 春風駘蕩(しゅんぷうたいとう):
春の風がのどかに吹く様子。そこから転じて、人の性質や態度が温和でのんびりしているさま。 - 春日遅々(しゅんじつちち):
春の日が長く、のんびりとしている様子。うららかな春の日の情景を表す言葉。 - 春和景明(しゅんわけいめい):
春の気候が穏やかで、景色が明るく美しい様子。春ののどかで快い情景をいう言葉。 - 三寒四温(さんかんしおん):
冬の終わりから春先にかけて、寒い日が3日ほど続くと、次の4日ほどは暖かい、という気候が繰り返される現象。
「夏」のことわざ・慣用句、四字熟語
夏は、太陽が輝き、活動的になる季節。暑さや、自然の力強さを表す言葉があります。

「夏」のことわざ・慣用句
- 夕立は馬の背を分ける(ゆうだちはうまのせをわける):
夏の夕立が、馬の背の片側は濡れても反対側は濡れないほど、ごく狭い範囲に局地的に降る様子。 - 蝉時雨(せみしぐれ):
多くの蝉が一斉に鳴きたてる声を、時雨(しぐれ)が降る音にたとえた言葉。夏の盛りの情景を象徴する。 - 夏の短夜(なつの みじかよ):
夏至の頃は日中の時間が長く、夜が短いこと。また、その短い夏の夜のこと。 - 青嵐(あおあらし/せいらん):
初夏に青葉を揺らして吹き渡る、やや強い風。夏の季語としても使われる。 - 秋風が立つ(あきかぜがたつ):
文字通りには秋風が吹き始めること。夏の終わりを感じさせる言葉。また、男女間の愛情が冷めたり、人気の盛りを過ぎたりすることのたとえにも使われる。
「夏」の四字熟語
- 夏炉冬扇(かろとうせん):
夏期の火鉢(炉)と冬期の扇。季節外れで役に立たない物事のたとえ。 - 緑樹濃陰(りょくじゅのういん):
緑の木々が生い茂り、濃い木陰を作っている様子。夏の木陰の涼しさを感じさせる言葉。
「秋」のことわざ・慣用句、故事成語、四字熟語
秋は、涼しくなり、実りの季節。落ち着きや、もののあわれを感じさせる言葉があります。

「秋」のことわざ・慣用句
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし):
秋は日没が早く、太陽があっという間に沈んでしまう様子を、井戸の釣瓶が早く落ちるさまにたとえた言葉。 - 女心と秋の空(おんなごころとあきのそら):
秋の天候が変わりやすいように、女性の愛情や気持ちも移ろいやすいことのたとえ。 - 天高く馬肥ゆる秋(てんたかくうまこゆるあき):
秋は空が澄み渡って高く見え、馬も食欲を増して肥えるほど気候が良いということ。実り豊かな秋を表す言葉。 - 暑さ寒さも彼岸まで(あつささむさもひがんまで):
夏の暑さも秋の彼岸(秋分の日前後)までには和らぎ、冬の寒さも春の彼岸までには落ち着くということ。
※春の項でも触れましたが、秋の季節の区切りとしても重要です。 - 秋の夜長(あきのよなが):
秋分を過ぎると、日照時間が短くなり夜が長くなること。また、その長い秋の夜。 - 灯火親しむべし(とうかしたしむべし):
秋の夜長は涼しく、灯りの下で読書をするのに適している、という意味。秋の夜の過ごし方を表す言葉。
(「秋燈親しむべし」とも) - 物思う秋(ものもうあき):
秋はなんとなく物思いにふけったり、感傷的な気分になったりしやすいということ。 - 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな):
秋ナスは美味なので嫁には食べさせたくないという嫁いびりの意味、体を冷やすので大事な嫁には食べさせない方が良いという配慮の意味など、諸説あることわざ。 - 〇〇の秋:
「スポーツの秋」「食欲の秋」「読書の秋」「芸術の秋」など、秋が特定の活動に適していることを示す慣用的な表現。
「秋」の故事成語
- 一葉落ちて天下の秋を知る(いちようおちててんかのあきをしる):
一枚の桐の葉が落ちるのを見て、秋の到来を知るという意味。わずかな前兆から、物事の本質や全体の趨勢(すうせい)、衰亡などを察知することのたとえ。
(梧桐一葉:ごどういちよう とも関連)
「秋」の四字熟語
- 秋高気爽(しゅうこうきそう):
秋空が高く澄み渡り、空気がさわやかであること。秋の快適な気候を表す言葉。
(「天高く気爽やか」とも読む)
「冬」のことわざ・慣用句、四字熟語
冬は、寒さが厳しく、生命が息を潜める季節。忍耐や、備えの大切さを説く言葉があります。

「冬」のことわざ・慣用句
- 冬来たりなば春遠からじ(ふゆきたりなばはるとおからじ):
イギリスの詩人シェリーの詩の一節から。「厳しい冬が来たということは、暖かい春も遠くない」という意味。つらい時期を耐え忍べば、必ず希望のある時期が来るという励ましの言葉。 - 雪は豊年の瑞(ゆきはほうねんのしるし):
冬に雪が多く降ると、雪解け水が豊富になり、また雪が害虫を駆除してくれるため、その年は豊作になるという言い伝え。「瑞」は吉兆の意味。 - 雪は夜の内に降れ(ゆきはよのうちにふれ):
雪が降るなら、人々の生活や交通への影響が少ない夜のうちに降ってほしい、という雪国の人々の切実な願いを表した言葉。 - 冬の雷は役に立たぬ(ふゆのらいはやくにたたぬ):
冬に鳴る雷は、夏の雷と違って雨を伴わないことが多く、農作物に恩恵をもたらさないことから言われる。 - 冬将軍(ふゆしょうぐん):
厳しい冬の寒さを擬人化した言葉。シベリア寒気団など、厳しい寒波の到来を指して使われることが多い。 - 枯れ木も山の賑わい(かれきもやまのにぎわい):
つまらないものでも、ないよりはましであることのたとえ。冬枯れの寂しい山の景色に、枯れ木でもあれば少しは賑わいが出ることから。 - 六花(りっか/むつのはな):
雪の結晶が六角形であることから、雪の雅称(美称)として使われる言葉。
「冬」の四字熟語
- 雪中松柏(せっちゅうしょうはく):
雪の中でも、松や柏(この場合はコノテガシワなどの常緑樹)が緑の色を変えないことから、志や節操が固く、逆境にあっても屈しないことのたとえ。 - 一陽来復(いちようらいふく):
陰が極まって陽が戻ってくること。冬至(一年で最も昼が短い日)を境に日が長くなっていくことから、冬が去り春が来ること、または悪いことが続いた後にようやく良い方へ向かうことを意味する。
四季の移ろいと自然の言葉
春夏秋冬、それぞれの季節の言葉を見てきました。
最後に、一年を通じた季節が移り変わる様子や、四季を通じて感じられる自然の美しさ、そしてそこから連想される考え方を捉えた言葉に触れてみましょう。
「四季」のことわざ・慣用句
- 雪月花(せつげつか):
冬の雪、秋の月、春の花。それぞれ趣の異なる季節の美しい自然物の代表として挙げられるもの。四季の移り変わりの中で、それぞれの季節の美を愛でる風流な心持ちを表します。 - 四季折々(しきおりおり):
春・夏・秋・冬のそれぞれの季節ごと、という意味。
「折々」はその時々を指し、季節が巡る中で時期に応じて変化する様子や、それぞれの季節に特有の風情があることを示します。
「四季」の四字熟語
- 花鳥風月(かちょうふうげつ):
美しい自然の風景や風物全般のこと。花(春・夏)、鳥(通年)、風(通年)、月(秋・冬)といった自然の要素を通して、四季折々の風雅な趣を楽しむ心を表現しています。 - 山紫水明(さんしすいめい):
日に照らされた山が紫色に見え、川の水が清らかに澄んでいる、美しい自然の景色のこと。特定の季節に限定されず、四季を通じて美しい日本の自然風景を表す言葉として使われます。 - 栄枯盛衰(えいこせいすい):
草木が茂っては枯れるように、人の世の栄華と衰退は繰り返されるということ。季節の移り変わりに見られる盛衰のサイクルを、人生や世の中の変転になぞらえた言葉です。 - 諸行無常(しょぎょうむじょう):
この世のあらゆる現象は絶えず変化し、同じ状態に留まるものはないということ。季節が巡り、自然が姿を変えていく様子に重ねて、この世の真理として語られます。(仏教語) - 万物流転(ばんぶつるてん):
宇宙に存在するすべてのものは、絶えず変化し移り変わっていくということ。季節の循環も、この大きな流れの一部として捉えられます。
まとめ – 季節の言葉と、豊かな時間
春夏秋冬、そして巡る季節を表す言葉たち。
そこには、日本の美しい自然と、先人たちが育んできた繊細な感性が、今も静かに息づいています。
これらの言葉を心に留めておくことで、日常の何気ない風景が少し違って見えたり、季節の確かな移ろいの中に、新たな発見や心の動きを感じたりするかもしれません。
忙しい毎日だからこそ、時にはこうした言葉を思い出し、自然が織りなす時間の豊かさに、そっと耳を澄ませてみてはいかがでしょうか。

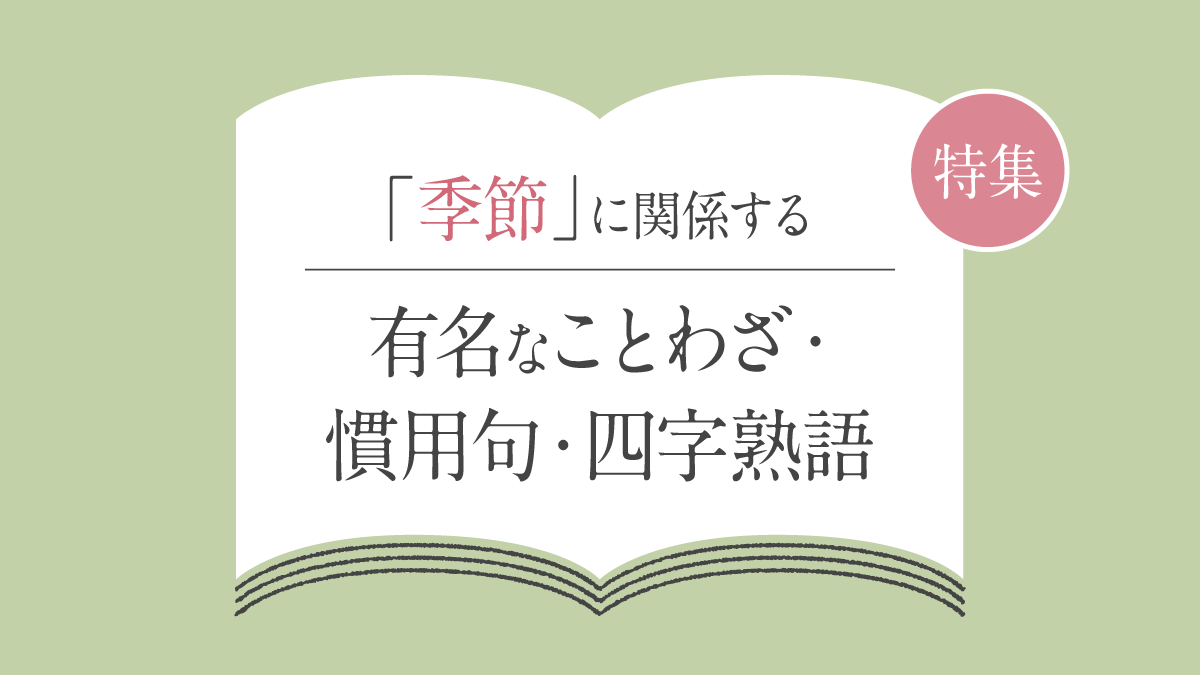
コメント