人の顔立ちや魅力を表現する言葉は数多くありますが、「男の目には糸を引け女の目には鈴を張れ」という、少し独特なことわざを聞いたことがあるでしょうか。
これは、かつての日本で理想とされた男女の目の特徴を表した言葉です。
しかし、現代の価値観から見ると注意が必要な表現でもあります。
この記事では、このことわざの意味や背景、そしてなぜ現代での使用に注意が必要なのかを解説します。
「男の目には糸を引け女の目には鈴を張れ」の意味
このことわざは、「男性の目は細く切れ長であるのが良く、女性の目は鈴のように丸くぱっちりしているのが魅力的である」 という意味です。
- 「糸を引け」:細く、すっと横に伸びたような切れ長の目を指します。理知的で意志の強そうな印象を与える目つきとされました。
- 「鈴を張れ」:鈴のように丸く、黒目が大きくぱっちりとした目を指します。愛嬌があり、感情豊かに見える印象を与える目つきとされました。
つまり、この言葉は、男女それぞれの理想的な目の形についての、当時の美意識を示したものです。
「男の目には糸を引け女の目には鈴を張れ」の語源 – 昔の美意識を反映
このことわざがいつ、どのようにして生まれたのか、その正確な起源は定かではありません。
しかし、江戸時代の浮世絵などに描かれた人物像を見ると、男性は切れ長の涼しげな目元で、女性は丸く愛らしい目で描かれることがしばしばあります。
これは、当時の人々が抱いていた男女の理想像や美意識を反映していると考えられます。
「糸を引く」ような細い目は知性や冷静さ、「鈴を張る」ような丸い目は愛嬌や優しさを連想させ、それが伝統的な男女の役割分担のイメージ(男性は理性的、女性は感情豊か)と結びついて、理想的な目の形として定着していったのかもしれません。
「男の目には糸を引け女の目には鈴を張れ」が使われる場面と例文
現代において、このことわざが日常会話や一般的な文章で使われることは、ほとんどありません。
もし使われるとすれば、それは過去の美意識や文化、あるいは古い文学や絵画に描かれた人物の特徴を解説するような、限定的な文脈でしょう。
安易にこの言葉を使うことは、性差別的と受け取られる可能性が非常に高いため、避けるべきです.
(引用としての)例文
- 「古い時代の美人画を見ると、女性の目は丸く大きく描かれていることが多い。まさに『女の目には鈴を張れ』という価値観が表れている。」
- 「彼は、時代劇に出てくる武士のような、『男の目には糸を引け』と言われたような涼しい目元をしている。」
※上記はあくまで過去の価値観を示す文脈での引用例であり、人物評価として現代で使うことは推奨されません。
類義語
このことわざのように、男女別に特定の容姿を理想とする直接的な類義語はほとんどありません。
顔立ちの美しさを表す一般的な言葉としては、以下のようなものがあります。
- 眉目秀麗(びもくしゅうれい):眉や目が整っていて美しいさま。男女を問わず用いられる。
- 目千両(めせんりょう):目が美しいことは千両の価値があるほど素晴らしいということ。目の魅力を称賛する言葉。
対義語
このことわざに直接的な対義語はありません。
しかし、この言葉が示す「男女で理想の目の形はこうあるべき」という固定的な美意識に対立する考え方として、以下の概念が挙げられます。
- 美の多様性:美しさの基準は一つではなく、人それぞれ多様であるという考え方。
- 個性:他の人とは違う、その人ならではの特徴や魅力。画一的な基準にとらわれない価値観。
英語での類似表現
英語圏の文化には、このように男女で理想的な目の形を具体的に示すことわざや慣用句は存在しません。
美しさに関する表現は文化によって大きく異なります。
美の基準の主観性を示す表現としては、以下のようなものがあります。
- Beauty is in the eye of the beholder.
意味:「美は見る人の目の中にある」。何が美しいかは、それを見る人によって異なる、という考え方。
このことわざが示す画一的な美意識とは対照的です。
「男の目には糸を引け女の目には鈴を張れ」を使う上での注意点 – 現代における問題点
このことわざを理解し、言及する上で、最も重要な注意点があります。
この表現は、現代の価値観においては性差別的であり、不適切とみなされます。
- 固定的・差別的なジェンダー観:
この言葉は、「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」という固定的な性別役割や外見のステレオタイプを助長します。
人の魅力を性別によって限定し、画一的な美意識を押し付けるものであり、ジェンダー平等の考え方に反します。 - 容姿への偏見:
特定の目の形だけを理想とし、それ以外を劣っているかのように示唆することは、容姿に対する偏見(ルッキズム)に繋がりかねません。 - 使用は厳に慎むべき:
日常会話や公の場、文章などでこのことわざを用いることは、相手に不快感を与えたり、差別的な意図があると誤解されたりする可能性が極めて高いです。絶対に避けるべき表現と言えます。
もし、歴史的な文脈や文学・美術の解説などでこの言葉に触れる必要がある場合は、それが過去の価値観に基づく表現であることを明確にし、批判的な視点を持って扱うことが不可欠です。
まとめ – 過去の価値観として知る言葉
「男の目には糸を引け女の目には鈴を張れ」は、かつての日本社会における男女の理想的な目の形を表したことわざです。
浮世絵などにもその影響が見られ、当時の美意識やジェンダー観をうかがい知ることができます。
しかし、その根底にあるのは、現代では受け入れられない固定的な性別役割分担の意識や、画一的な美の基準です。人の魅力は多様であり、性別によって外見の理想を決めつけることは、個性を尊重する現代の考え方とは相容れません。
この言葉は、あくまで過去の価値観を示す歴史的な表現として捉え、現代社会で安易に使用することは厳に慎むべきです。
美しさの基準は人それぞれであり、多様な個性が尊重される社会を目指す上で、この言葉が持つ問題点を理解しておくことが大切です。


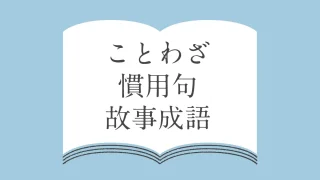
コメント