犬や猫などが、用を足した後に後ろ足で砂を蹴って去っていく。
そんな仕草を見たことがあるでしょうか。「後足(あとあし)で砂をかける」という慣用句は、まさにそのような動物の行動から生まれた表現です。
しかし、この言葉は単なる動物の描写ではありません。
人間関係における、ある種の非礼な行為を指して使われます。
今回は、「後足で砂をかける」の意味や由来、使い方、そして関連する言葉について掘り下げていきましょう。
「後足で砂をかける」の意味・教訓
「後足で砂をかける」とは、世話になった人や場所を去る際に、感謝するどころか最後に迷惑や損害を与えたり、悪口を言ったりするような恩知らずで非礼な行為をすることです。
お世話になったにも関わらず、去り際に相手を不快にさせたり不利益をもたらしたりする。
そのような、これまでの関係を台無しにするような裏切り行為を指します。
この慣用句は、そうした行為がいかに恩知らずで、道義にもとるものであるかを非難する意味合いで使われます。
「立つ鳥跡を濁さず」という、去り際の美学とは正反対の行動と言えるでしょう。
「後足で砂をかける」の語源
この慣用句の語源は、文字通り犬や馬などが、走り去る時に後ろ足で砂や土を蹴り上げる様子に由来するとされています。
動物が去り際に砂を蹴る行為は、特に悪意があるわけではなく、単なる習性や無頓着な行動です。
しかし、その様子が、後に残る者のことなど顧(かえり)みずに、配慮なく立ち去っていく人間の態度に重ねられました。
そこから転じて、世話になった恩を忘れ、去り際に相手に不快感を与えたり、迷惑をかけたりする非礼な行為を指すようになったと考えられています。
「後足で砂をかける」が使われる場面と例文
この慣用句は、主に人間関係の終わりや、組織から離れる場面などで、去っていく側の非礼な行動を批判する際に使われます。
- 退職する際に、会社の悪口を言いふらしたり、情報を持ち出したりする行為
- 世話になった恩人の顔に泥を塗るような行動をとって、関係を断つ場合
- 引っ越す際に、隣人に挨拶もせず、ゴミなどを残していくような行為
例文
- 「彼は長年勤めた会社を辞める際に、顧客情報を持ち出したらしい。まさに後足で砂をかけるような真似だ。」
- 「あれほどお世話になった先輩に対して、あんな酷い別れ方をするなんて、後足で砂をかけるにも程がある。」
- 「プロジェクトから抜けるのは仕方ないが、最後にデタラメな情報を流すとは。後足で砂をかけるようなことはやめてほしい。」
- 「喧嘩別れした挙句、共通の友人にまで悪口を言いふらすなんて、彼女は後足で砂をかけるような人だった。」
「後足で砂をかける」の類義語・関連語
「後足で砂をかける」と似た意味を持つ言葉や、関連する表現を見てみましょう。
- 恩を仇で返す:受けた恩に対して、感謝するどころか害を与えること。「後足で〜」は特に去り際の行為を指しますが、「恩を仇で返す」はより広い意味での裏切り行為を指します。
- 恩知らず:受けた恩を忘れ、感謝の心がないこと、またそのような人。「後足で砂をかける」のは、恩知らずな人がとりがちな行動の一つです。
- 捨て台詞(すてぜりふ):去り際に、相手への悪口や皮肉などを言い放つこと。「後足で砂をかける」行為の一部とも言えます。
- 非礼(ひれい):礼儀に反すること。失礼なこと。
- 絶縁(ぜつえん):関係を断ち切ること。
「後足で砂をかける」の対義語
反対の意味を持つ言葉としては、以下のようなものが考えられます。
- 立つ鳥跡を濁さず:立ち去る者は、見苦しくないように後始末をきちんとしていくべきである、というたとえ。去り際の美学を示す言葉で、「後足で〜」とは正反対の姿勢です。
- 円満退社:勤めていた会社などから、特に問題を起こすことなく、良好な関係を保ったまま辞めること。
- 恩に報いる:受けた恩に対して、感謝の気持ちを行動で示すこと。去り際に感謝を示す行為は、これにあたります。
- 有終の美を飾る:物事を最後までやり遂げ、立派な成果で締めくくること。関係の終わり方を美しくすることも含まれる場合があります。
「後足で砂をかける」の英語での類似表現
英語で「後足で砂をかける」のニュアンスに近い表現を探してみましょう。去り際の非礼な行為や関係破壊を表す表現があります。
- To burn one’s bridges (behind one).
- 意味:(自分の後ろの)橋を焼く。
- 関係を修復不可能にする、戻る道を断つ、という意味。特に、去り際に敵対的な行動をとって、元の場所や人々との関係を悪化させるニュアンスで使われることがあります。
- To slam the door in someone’s face.
- 意味:誰かの顔の前でドアをバタンと閉める。
- 関係を突然、無礼に断ち切る様子を表します。
- It’s like kicking sand in someone’s face.
- 意味:誰かの顔に砂を蹴りかけるようなものだ。
- これは比喩的な表現で、侮辱的で卑劣な行為を指す際に使われることがあり、「後足で砂をかける」状況にも当てはまる場合があります。(ただし、一般的なイディオムではありません)
これらの表現は、「後足で砂をかける」が持つ、去り際の非礼さや関係破壊のニュアンスを伝えることができます。
まとめ – 去り際にこそ見せるべき誠意
「後足で砂をかける」は、お世話になった場所や人に対して、去り際に恩を仇で返すような非礼な行為をすることを戒める慣用句です。
人間関係の終わり方や、組織からの去り際には、その人の本質が現れるとも言われます。
たとえ何らかの不満があったとしても、最後に相手を不快にさせたり、迷惑をかけたりする行為は、これまでの関係性や自分自身の品位をも損ねてしまいます。
「立つ鳥跡を濁さず」という言葉があるように、去り際はできる限りきれいに、感謝の気持ちを持って締めくくりたいものです。
それが、これまでお世話になった方々への最低限の礼儀であり、ひいては自分自身の未来のためにも繋がるのではないでしょうか。この慣用句を反面教師として、誠意ある行動を心がけたいものですね。


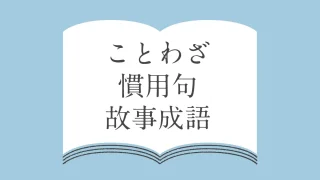
コメント