もくじ
意味 – 人の話を聞き流すこと
「馬耳東風」とは、他人の意見や忠告、批評などを聞いても、まったく心に留めずに聞き流してしまうことのたとえです。
まるで馬の耳(馬耳)に心地よい春の風(東風)が吹いても、馬が何も感じないように、人の言葉が少しも効果を発揮しない様子を表します。
語源 – 李白の詩と春風
「馬耳東風」の語源は、中国・唐の時代の高名な詩人、李白(701-762)が詠んだ詩にあります。
- 馬耳(ばじ):馬の耳。
- 東風(とうふう):東から吹く風、すなわち春風のこと。
李白は、自身の優れた詩が世間の人々に理解されない状況を、
「まるで春風が馬の耳を吹き抜けても、馬が何も感じないようなものだ」と詩の中で表現しました。
この一節から、「馬耳東風」は、人の意見や忠告などを聞いても、全く意に介さず聞き流してしまう態度のたとえとして使われるようになったのです。
使われる場面と例文 – 忠告や意見を意に介さない態度
「馬耳東風」は、主に、誰かが忠告やアドバイス、重要な話をしても、相手がそれを真剣に受け止めず、全く意に介さない、あるいは聞き流してしまう態度に対して使われます。
例文
- 「何度注意しても、彼は馬耳東風で、全く態度を改めようとしない。」
- 「親が心配してアドバイスしても、息子は馬耳東風といった様子でゲームに夢中だ。」
- 「会議で貴重な意見が出ても、社長は馬耳東風とばかりに聞き流してしまった。」
- 「彼女にいくら説明しても、馬耳東風で、少しも分かってもらえない。」
類義語 – 聞き流す・無関心な様子
- 馬の耳に念仏(うまのみみにねんぶつ):馬にありがたい念仏を聞かせても意味がないように、いくら意見や忠告をしても効果がないことのたとえ。「馬耳東風」とほぼ同じ意味で使われます。
- 糠に釘(ぬかにくぎ):柔らかい糠に釘を打っても手応えがないように、何をしても全く効き目や反応がないことのたとえ。
- 蛙の面に水(かえるのつらにみず):蛙の顔に水がかかっても平然としているように、どんな仕打ちや非難を受けても、全く平気でいることのたとえ。「馬耳東風」よりも、厚かましさや面の皮の厚さといったニュアンスが加わることがあります。
- 暖簾に腕押し(のれんにうでおし):暖簾を腕で押しても手応えがないように、力を入れても張り合いがなく、効果が上がらないことのたとえ。
対義語 – 熱心に耳を傾ける姿勢
- 傾聴(けいちょう):相手の話の内容だけでなく、その気持ちにも注意を払いながら、熱心に耳を傾けること。
- 言聴計従(げんちょうけいじゅう):人の言うことをよく聞き入れ、その計画や提案に従うこと。素直に意見を受け入れる様子。
- 虚心坦懐(きょしんたんかい):心に何のわだかまりもなく、ありのままで素直な心を持っていること。人の意見を受け入れやすい状態を指します。
英語での類似表現 – 聞こえないふり
人の話を聞き流したり、意に介さなかったりする様子を表す英語表現には、以下のようなものがあります。
- turn a deaf ear (to…)
意味:(~に対して)聞く耳を持たない、故意に聞こえないふりをする。 - (go) in one ear and out the other
意味:(話などが)一方の耳から入って、もう一方の耳からそのまま出ていく。全く記憶に残らない、聞き流される様子。 - like water off a duck’s back
意味:アヒルの背中にかかった水のように、(忠告・非難などが)全く効き目がない、平気であること。「蛙の面に水」に近い表現です。
まとめ
「馬耳東風」は、人の意見や忠告を聞き流す態度を指す四字熟語で、中国・唐代の詩人・白居易の詩に由来します。
多くの場合、相手の態度を非難するニュアンスを含むため、使用には注意が必要です。
特に、目上の人に対して使うのは失礼にあたる可能性が高いため、場面や相手との関係性を考慮することが大切です。
言葉の意味を正しく理解し、適切な状況で使い分けることを心がけましょう。

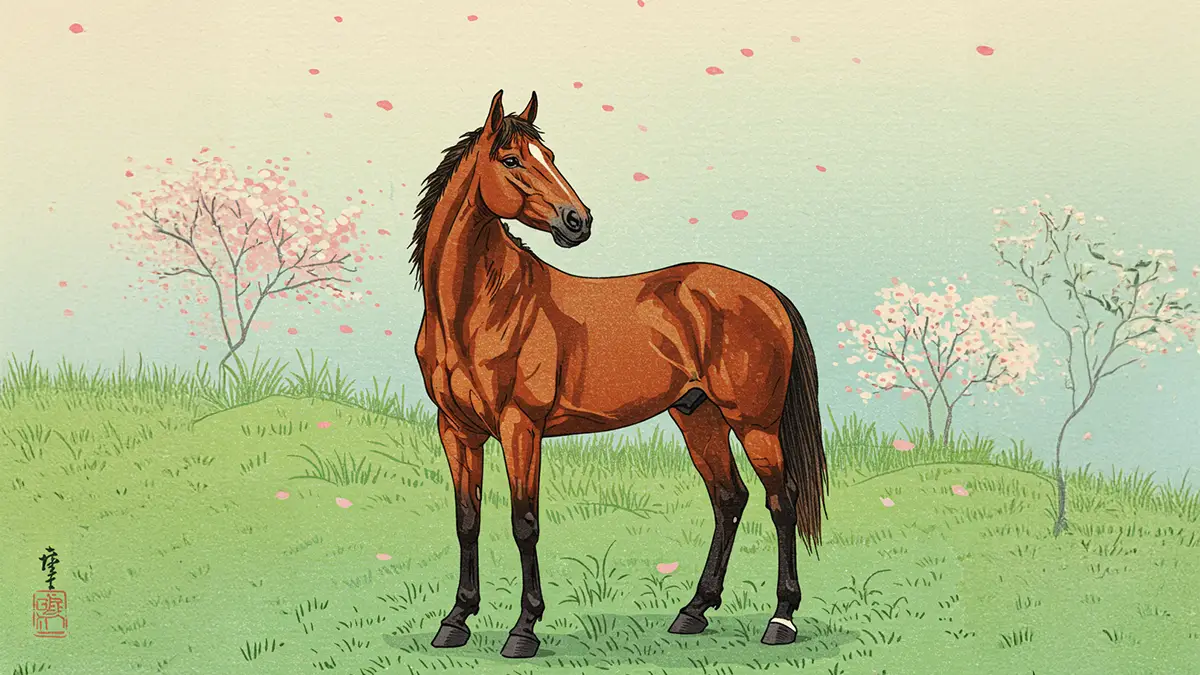
コメント