「木を見て森を見ず」「枯れ木に花」「青木に竹を接ぐ」など、日本語には「木」を使ったことわざや慣用句が数多く存在します。
私たちの日常会話に自然と溶け込んでいるこれらの表現ですが、その正確な意味や由来をご存知でしょうか?
本記事では、日本語の豊かな表現力を感じられる「木」にまつわることわざ・慣用句を厳選し、意味や使い方、例文までわかりやすく解説します。
ビジネスシーンでも使える表現から、日本の伝統文化を反映した言葉まで、言葉の知識を深めたい方必見の内容です。
「木」のことわざ・慣用句一覧
ここでは、「木」を使ったことわざ・慣用句を、その意味と例文とともにご紹介します。
木を見て森を見ず (きをみてもりをみず)
- 意味: 細部にとらわれて全体像を見失うこと。
- 例文: 彼は木を見て森を見ず、プロジェクトの全体目標を見失っている。
枯れ木に花 (かれきにはな)
- 意味: 衰えたものが再び栄えること、または望みがないと思われることに奇跡が起こることのたとえ。
- 例文: 倒産寸前だった会社が、新技術の開発で枯れ木に花を咲かせた。
木に縁りて魚を求む (きによりてうおをもとむ)
- 意味: 方法が間違っていては目的を達成できないことのたとえ。
- 例文: 資金も技術もないのに、1週間で月に行くロケットを作ろうとするのは、木に縁りて魚を求むに等しい。
大木の下に小木育つ (たいぼくのもとにしょうぼくそだつ)
- 意味: 優れた人物のもとでは、自然と立派な人材が育つことのたとえ。
- 例文: あの教授の研究室は、大木の下に小木育つ環境だ。
木に竹を接ぐ (きにたけをつぐ)
- 意味: 物事のつながりが不自然なこと、筋が通らないことのたとえ
- 例文: 彼の話は木に竹を接いだようで、まったく理解できない。
枯れ木も山の賑わい (かれきもやまのにぎわい)
- 意味: つまらないものでも、ないよりはましであることのたとえ。
- 例文: 参加者が少ないが、枯れ木も山の賑わいだと思って参加しよう。
大木は風に折られる (たいぼくはかぜにおられる)
- 意味: 地位や能力が高い人ほど、ねたみや中傷を受けやすいことのたとえ。
- 例文: 彼は若くして社長になったが、大木は風に折られるというから心配だ。
良禽は木を択ぶ (りょうきんはきをえらぶ)
- 意味: 賢い鳥は自分がとまる木をよく選ぶように、賢明な人は仕える主君をよく選ぶものだというたとえ。
- 例文: 良禽は木を択ぶというから、君も就職先は慎重に選びなさい。
栴檀は双葉より芳し (せんだんはふたばよりかんばし)
- 意味: 優れた人物は、幼いときから優れていることのたとえ。(栴檀は香木)
- 例文: 彼は幼い頃から才能を発揮しており、栴檀は双葉より芳しだ。
十年樹木、百年樹人 (じゅうねんじゅぼく、ひゃくねんじゅじん)
- 意味: 人材育成には長い年月がかかることのたとえ。
(樹木は10年で用材になるが、人材育成には100年かかる) - 例文: 教育は、十年樹木、百年樹人というように根気のいる仕事だ。
木で鼻をくくる(きではなをくくる)
- 意味: 非常に無愛想な態度をとること。冷淡にあしらうこと。
- 例文: 「受付で木で鼻をくくったような対応をされた。」
株を守りて兎を待つ(くいぜをまもりてうさぎをまつ)
- 意味: 古い習慣にとらわれて、進歩がないこと。融通がきかないことのたとえ。
- 例文: いつまでも昔のやり方に固執するのは、株を守りて兎を待つようなものだ。
(切り株にぶつかって死んだウサギをもう一度得ようと、来る日も来る日も切り株を見張っていた人がいた、という話)

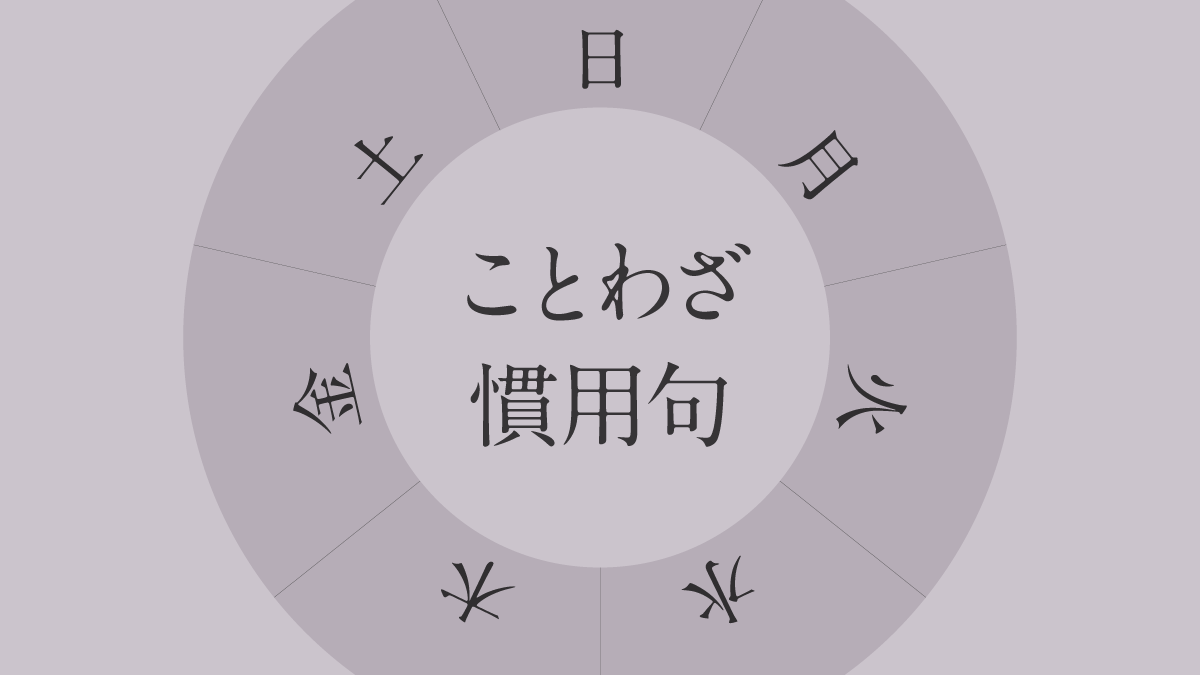
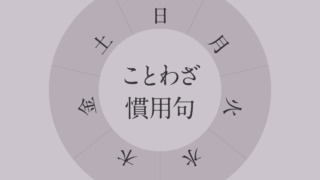
コメント