日本語には、花や植物、野菜、果物の名前が入ったことわざや慣用句、四字熟語がたくさんあります。
これらは昔から私たちの生活に深く根付いており、その成長や特徴が、人の感情やさまざまな状況を表すのに使われてきました。
今回は、日常会話でも使いやすく比較的有名なものを厳選し、カテゴリ別にご紹介します。
花
- 高嶺の花(たかねのはな):
手が届かない、憧れの存在のたとえ。 - 花より団子(はなよりだんご):
風流よりも実益を選ぶことのたとえ。 - 立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花
(たてばしゃくやく すわればぼたん あるくすがたはゆりのはな):
女性の美しい立ち居振る舞いを花にたとえた言葉。 - 梅に鶯(うめにうぐいす):
取り合わせの良いもの、仲の良い間柄のたとえ。 - 落花流水(らっかりゅうすい):
男女が互いに慕い合うことのたとえ。
落花は流水に従って流れ、流水は落花を浮かべて流れるさまから。 - 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿(さくらきるばか、うめきらぬばか):
桜と梅の剪定方法の違いを述べ、それぞれの特性に応じた手入れが必要であることのたとえ。 - 世の中は三日見ぬ間の桜かな(よのなかはみっかみぬまのさくらかな):
世の中の移り変わりが早いことのたとえ。 - 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり):
どんな女性でも年頃になれば、それなりの魅力があることのたとえ。 - 柳は緑、花は紅(やなぎはみどり、はなはくれない):
自然のありのままの姿が美しいこと。
また、物事にはそれぞれ固有の特性があることのたとえ。 - 両手に花(りょうてにはな):2つのよいものを同時に手に入れることのたとえ。また、1人の男性が2人の女性を連れている様子をたとえる言葉。
- 六日の菖蒲十日の菊(むいかのあやめとおかのきく):物事が時期に遅れて用がなくなってしまうこと。
植物
- 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし):
藍という植物からとれる染料の青色は、元の藍の色よりもさらに鮮やかであることから、弟子が師匠を超えることのたとえ。 - 栴檀は双葉より芳し(せんだんはふたばよりかんばし):
優れた人物は幼い頃から才能の片鱗を見せることのたとえ。 - 実るほど頭を垂れる稲穂かな(みのるほどこうべをたれるいなほかな):
立派な人ほど謙虚であることのたとえ。 - 大樹の陰(たいじゅのかげ):
力のある人の庇護のもとにいることの安心感、またはその恩恵のたとえ。 - 柳に風(やなぎにかぜ):
相手に逆らわず、うまくあしらうことのたとえ。 - 草の根分けても(くさのねわけても):
どんな手段を使っても探し出すことのたとえ。 - 根も葉もない(ねもはもない):
全く根拠がないことのたとえ。 - 枯れ木も山の賑わい(かれきもやまのにぎわい):
つまらないものでも、ないよりはましであることのたとえ。 - 木に竹を接ぐ(きにたけをつぐ):
物事のつながりが不自然で、ちぐはぐなことのたとえ。 - 竹を割ったよう(たけをわったよう):
性格がさっぱりとしていて、まっすぐなことのたとえ。 - 竹馬の友(ちくばのとも):
幼なじみのこと。 - 綿に針を包む(わたにはりをつつむ):
外見は穏やかだが、内心に悪意や敵意を隠していることのたとえ。 - 雨後の筍(うごのたけのこ):
雨上がりに筍が次々と生えてくるように、物事が相次いで現れることのたとえ。 - 一葉落ちて天下の秋を知る(いちようおちててんかのあきをしる):
わずかな前兆から、将来の大きな変化を察知することのたとえ。 - 草葉の陰(くさばのかげ):
死後の世界。墓の下。 - 青葉は目の薬(あおばはめのくすり):
新緑を見ると目が休まり、気分が安らぐこと。 - 枯れ木に花咲く(かれきにはなさく):
衰えたものが再び栄えること。
望み薄と思われたことが実現することのたとえ。 - 木を隠すなら森の中(きをかくすならもりのなか):
あるものを隠すには、同じようなものがたくさんある場所に隠すのが一番良いということ。 - 草枕(くさまくら):
旅先での仮寝のたとえ。 - 竹篦返し(しっぺがえし):
すぐに仕返しをすること。 - 木の股から生まれる(きのまたからうまれる):
出自がはっきりしないこと。道理に合わないことのたとえ。 - 火中の栗を拾う(かちゅうのくりをひろう):
自分の利益にならないのに、他人のために危険を冒すことのたとえ。
野菜・果物(フルーツ)
- 桃栗三年柿八年(ももくりさんねんかきはちねん):
何事も成就するには、相応の年月が必要であることのたとえ。 - 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな):
美味しい秋茄子を嫁に食べさせるのはもったいないという姑の嫁いびりの言葉。
または、秋茄子は体を冷やすので、嫁の体を気遣う言葉という二つの解釈がある。 - 柿が赤くなれば医者が青くなる(かきがあかくなればいしゃがあおくなる):
柿が実る秋は気候が良く、病人が減って医者が困るという意味。 - 瓜の蔓に茄子はならぬ(うりのつるになすびはならぬ):
平凡な親からは非凡な子は生まれないことのたとえ。 - 瓢箪から駒(ひょうたんからこま):
意外なところから意外なものが出ること。
冗談だと思っていたことが現実になることのたとえ。 - 青菜に塩(あおなにしお):
元気がなくなり、しょげている様子。 - 大根役者(だいこんやくしゃ):
演技が下手な役者のこと。大根は薬味などにも使われ、「当たらない」ものとして使われたことに由来。 - 親の意見と茄子の花は千に一つも無駄は無い(おやのいけんとなすびのはなはせんにひとつもむだはない):
親の言うことは子供にとってすべて有益で、よく聞けという教え
穀物
- 五穀豊穣(ごこくほうじょう):
穀物が豊かに実ること。 - 蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ):
原因がなければ結果は生じないことのたとえ。
まとめ
植物に関することわざや慣用句、四字熟語は、私たちの生活や文化に深く根付いています。
これらの言葉は、単なる比喩表現にとどまらず、人生の教訓や知恵を含んでいるものが多くあります。
植物の持つ生命力や、その姿から得られるインスピレーションは、言葉を通して私たちに多くのことを教えてくれます。
まとめ
花や植物、野菜、果物にまつわることわざや慣用句、四字熟語は、日本語の表現をより豊かにしてくれます。
これらの言葉を知ることで、会話や文章に深みが生まれるだけでなく、植物を通じて先人の知恵や文化にも触れることができます。
ぜひ、お気に入りの表現を見つけて、日常で活用してみてください。

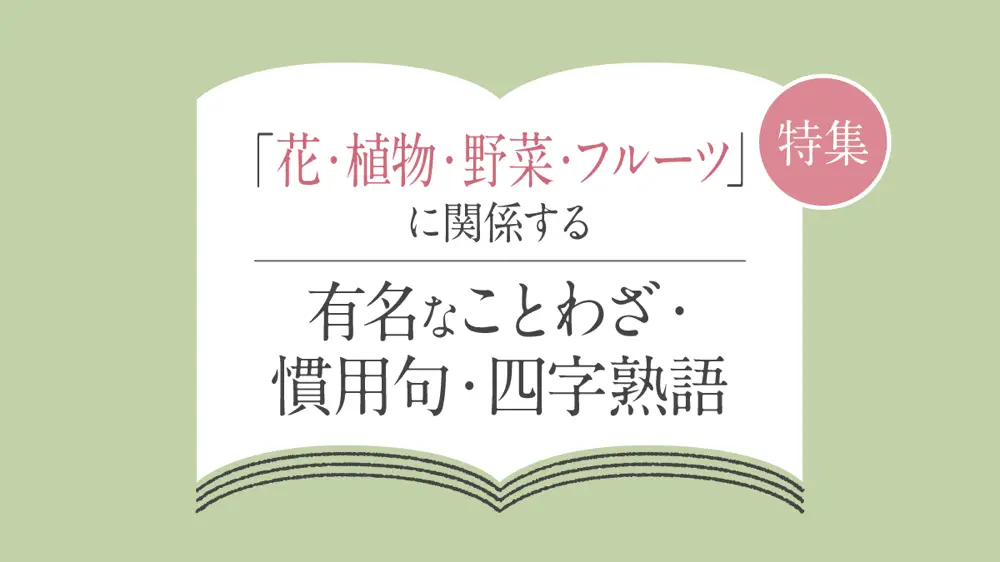
コメント